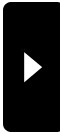2018年02月18日
『ふつうに学校にいくふつうの日』(コリン・マクノートン・文/きたむらさとし・絵/柴田元幸・訳)
 朝から青空の綺麗な日ですが,強い冷たい風が吹き続きました。
朝から青空の綺麗な日ですが,強い冷たい風が吹き続きました。天気予報では,「今日は全国的に気温が昨日よりも低,く真冬の寒さになりそうです。」と伝えていた通りに,当地でも,会う方がみな「寒い」「冷たい」と口にされた低温の一日でした。
今日は絵本です。
『ふつうに学校にいくふつうの日』(小峰書店・刊/世界の絵本コレクション)
ふつうに学校にいくふつうの日,
ふつうの男の子はふつうの夢からさめて,
ふつうのベッドからでて,
ふつうのおしっこをして,
ふつうに顔をあらって,ふつうの服をきて,
(略)
ふつうの学校にでかけました。
「でも,“ふつう”って何だろう?」
教室に登場した“新しい先生”ミスター・ギーは,子供達を「ふつうではない」ところへ導きました。
ふつうの男の子はかきはじめました。
知らないことばがつぎつぎとうかんできて,
なんの話か自分でもよくわからないまま,
どんどんかきつづけます。
せいいっぱい速くかいても,
ぜったいまにあいそうにありません。
ーーとにかく,いいたいことが多すぎるのです。
まるで,頭のなかでダムがこわれて,ことばが洪水になって
出てくるみたいで…。
ポーリン・クローフォードやビリー・ピアソンのような子もいたけど,“ふつう”ではない最高の授業になりました。
ミスター・ギーがしたことは…
小学校低学年で読める絵本ですが,大人の人にも楽しめる一冊です。
そして,“先生”にお薦めしたい一冊です。ミスター・ギーの考えたことは,あなたの考えのなかにありますか。
【今日の小咄】
ノートの最初のページを使わずに,2ページ目から書き始める人が多いことに気づいた友人が,「最初から1ページ目のないノートを売り出せば,紙の節約になるのに。」とつぶやいた。
【おまけ】
「もしもSiriが1980年代にあったら…」
現代では,AppleのCMで「What's a computer?」と言わせているように,コンピュータやインターネットは“生活の一部”になっている状況です。
そうした環境で生まれ育っている若者には,「これ何?」の話でしょう。
1980年代はMS-DOSコンピューターでした。その当時にSiriが開発され,使ったら…。
機種構成からインストール,起動…
当時を知る方には「そうだった」「これでも凄かった」など,笑いが止まらないかも…
◇iPad Pro — What’s a computer — Apple(YouTube)
2018年02月17日
「生きること」を考える(1991年)
 今日も天候の良い日でした。陽気に誘われて,梅花を愛でに行きましたが,ちょっと早かったようです。
今日も天候の良い日でした。陽気に誘われて,梅花を愛でに行きましたが,ちょっと早かったようです。“春の足音”を感じられる時期になり,よい天候が続いています。このまま,“いつもの春”になってくれると嬉しいのですが,どうでしょうか。
中学3年の授業参観(1991/01/22),最後の授業は「道徳」でした。
その日の学級通信は,「『生きること』を考える」の題名でした。
*********
昨日の学活の時間,答えるのが難しいアンケートをお願いしました。一つは『将来(未来)の夢』。これは,自分の将来を考えて答えてくれました。今日の通信の後半にまとめてあります。心配したのは,「平凡な生活」みたいな答えが多いのではないかということでした。でも,一人一人,なかなか夢のある希望をもっている人が多いので,安心しました。
二つ目が『“「いのち」「生きること」を大切にする”ためには何をしたらいいか。何ができるか』という質問でした。普段考えていることではないし,自分のことか,社会のことか,どこに重点を置いたらいいのか分からない。どんな答え方をしたら良いのか分からない。そんな質問で困った人が多かったようです。
書いてくれた人のものをとにかくまとめました。質問の仕方も悪いし,かっこいい答えや,いい子の答えを期待したわけではありませんから,答えはさまざまな内容になっています。
しかし,読んでいくと,困りながらも,考えて答えてくれているのが分かります。また,突然の質問にも関わらず,『生きること』について,実にさまざまなとらえ方があることも分かりました。
今日の道徳では,この「生きること」について,次の文章から考えてみたいと思います。昨日考えた「生きること」とは違った方向から,自分の「生きること」や「将来」を考える機会にしてみたいと思います。
一人の男と奥さんは,高山から移住してきたばかりです。二人は畑を耕し始めましたが,雨が降らず,作物は育ちませんでした。十分な食物をもっている人は,誰もいませんでした。(以下 アンケート結果・略)
奥さんは病気になり,とうとう食物がないために死にそうな状態になりました。
村にはたった一軒の食品店しかなく,店の主人は食物にたいへん高い値をつけました。夫は店の主人に,奥さんのために食物を少しわけてもらえるように頼みました。そして,後でお金を払うと言いました。
しかし,店の主人は次のように言いました。
「前金で払わない限り,何一つ食べ物はあげられない。」
男は,ずべての村人に食物を分けてくれるように頼みましたが,誰もそれだけの食物をもっていませんでした。
男は絶望的になり,奥さんのために食物を盗みに店に押し入りました。
「その夫は,そうすべきでしたか? その理由は?」
*********
現在と1991年とでは環境が大きく変わっており,設定や内容を変える必要があるでしょうが,今の中学生は,どう考えるでしょうか。
あなたは,夫の行動をどう思いますか。
この続きは,別の機会に。
2018年02月16日
卒業が近づいて(中学3年・1991年1月)
 今朝は雲が気になりましたが,晴れた日になり,陽の光に暖かさを感じる“春の日”でした。
今朝は雲が気になりましたが,晴れた日になり,陽の光に暖かさを感じる“春の日”でした。オリンピック(平昌五輪)では,アスリートの熱戦が繰り広げられています。
メダルや入賞を目標にしてきた選手は,その結果に,喜び,納得し,悔しがり…。観衆を感度させています。
テレビでも新聞でも,オリンピックを最初に大きく取り上げています。
オリンピックに関心があるし,競技結果が気になります。でも,その“報道”を素直に受け入れられずにいます。
先日,「マスコミの「メダルの期待がかかります」報道がスポーツをダメにする」(スピン経済の歩き方)の記事を読み,“モヤモヤ感”に説明が付けられたように思いました。
マスコミが“盛り上げる”のは「ものごとの“本質”」とは別のものになってしまい,それによって“壊れて”いるものが多いように感じています。
みなさんは,テレビの“報道”を見ていますか。
小学6年,中学3年,高校3年の「今」は,「卒業まで,あとわずか…」との思いで,「○○をしっかりと…」「思い出になる…」と生活や学習に向かっていることと思います。
中学3年の学級通信(1990・1991年)でも,冬休みを終え1月になって,そうした日記を載せています。
3学期が始まってすぐの1月11日の日記から。
Aさんこの日記に,こんな言葉を書いています。
中学校生活もあと60日。この中学生日記も最後の一冊となった。あと60日,どんなふううに思い出を記録していこうかなあ。
中学校生活もあと少しなんだけど,なんといっても入試までの日が,もうほんのちょっとしかない。もう,“ラストスパート”をかけ始める時ですね。勉強をおろそかにして困るのは自分。精一杯がんばるぞー。
勉強と,もう二つ考えていることがある。
一.クラスのみんなと一緒にいられる期間も少ない。今までクラスマッチとかで,いい思い出がたくさんある。だけど,最後に,やっぱり何かもう一つ思い出づくりをしたいなあなんて思う。最後,みんなで盛り上がりたい。
二.これは,私自身が心にきめたこと。三年間お世話になったこの学校。きれいにして卒業したい。「たつ鳥跡をにごさず」なんていう言葉があった気がする。だから,たった15分のそうじを一所懸命やろうと思う。
Bくん
今日,そうじの時間,B君と話していました。「三学期は,そうじをいっしょうけんめいやるか。」と。
今までもいっしょうけんめいやって,校長先生にほめられた時もあったけど…。僕は,何か一つでも,いっしょうけんめいにできることがほしいから。
Cさん
なんか,ずるずると,とうとうここまで来てしまった。とうとう,あと二か月ちょっとで卒業する。その時には,もう,この中学生日記も終わりです。なんか,今までのことを振り返ると,私は何もしてないように感じる。だから,心にのこる大きな思い出をつくりたい。
勉強にいそがしくなるけど,でも,美術でも家庭科でも,何でもいい。私にしかできないことを見つけたいです。
入試も後悔なんてしないようにしたい。
********
※ 特別なことでなくていい。たった15分を大切に。
※ よく「目標をもって…」と聞きますし,私も言います。でも難しいkぉとですよね。目標を実現した時の喜びは,言葉では表せないものです。小さな目標,ささいなことであっても,その喜びがあります。目標の内容よりも,その喜びを求めて,人は努力するものだと思います。
********
今,卒業が近づいている子供達は,どのような思いをもって日々を過ごしているでしょう。
そして,その近くにいる“大人”のみなさんは,何を聞き,何を語り,何をされているでしょう。
2018年02月15日
「○○学問」を例えて
 「今日は晴れる」を予定していましたが,曇り空でした。残念。
「今日は晴れる」を予定していましたが,曇り空でした。残念。休日の日。ビデオを見たり,本を読んだり,だらった,ぼ~っとした一日でした。
「梅の木学問」,「楠学問」という言葉を聞いたことがありますか。
以前,“受験”に臨む中学生のことを考えていたときに出会った言葉です。
新聞のコラムに
梅の木は早く生長するが大木にはならないところから,進み方は早いが学問を大成させないで終わる学問。とありました。
そして,楠は生長するのは遅いが大木になるところから,進歩は遅いが着実に成長し大成する学問。
コラムでは,受験勉強を梅の木学問に例えており,若者には楠学問を目指してほしいと述べていました。
子供達が“難しいこと”を覚えており,“知識”を持っているようですが,一歩踏み込んで,「どう思う?」と問い続けると,「・・・」と黙ってしまうことがあります。
簡単に,考えることなく,「難しい」「わかりません」と返してくることもあります。
新学習指導要領が告示され,4月から小学校で移行措置が始まります。
「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」…その方策を考えるとき,梅の木学問と楠学問の意識(使い分け)が役立つように思います。
いかがでしょう。
【今日の小咄】
甲斐さんという人が,自分の名前を説明するのに「甲斐の国の甲斐です。」と言ったら,後日送られてきた郵便物は,「貝」さんになっていたらしい。
“貝の国”っていったいどこ?
2018年02月14日
理事会。「20の違い」は…。

今日も気温の低い朝でしたが,日中は青空が綺麗な晴れで,暖かい日になりました。
まだ田畑の地面は凍っており,“草木が芽吹いて”というのは先になりそうですが,木の枝先には,赤みが感じられるようになってきました。
季節は“春”
午前中,新城市遺族会理事会がありました。
年度末が近づき,本年度の会計状況,懸案についての検討でした。
○会長あいさつ話を進めていくなかで「不本意であるが…」といった言葉で話をされる方がありました。
○実行委員長より説明
○会計より報告
○検討
戦後72年が過ぎ,組織としてのあり方が“変わり目”を迎えているように思います。
先人が行ってきたこと,現在の状況,そしてこれからを考えるときに,「決断」と「行動」が求められているようです。
理事をはじめ関係の方々の理解と協力により,変化(変革?)が進んでいくことでしょう。
よろしくお願いします。
いろいろな場面で,“職場の多忙化”が言われます。
「忙しい」という言葉を聞くことがありますが,古いメモに「忙しい人」と「仕事ができる人」を対比した言葉がありました。
**************
《忙しい人》と《仕事ができる人》の20の違い
忙しい人は,いつも「忙しい,忙しい」を口癖のようにしています。他人が見ると,何でそんなに忙しいのかが分からなかったりするのですが(仕事の成果から見ると),本人は忙しいのでしょう。忙しいと言うことが,その人のモチベーション理由のように感じるくらいです。
それと比べると,仕事ができる人は,他人から見ると何かゆったり,自分のペースで仕事をしているように見えるが,結果として大量の仕事を行ったりしている。みなさんの周りにもそんな《忙しい人》と《仕事ができる人》はいないでしょうか?
《忙しい人》と《仕事ができる人》は何が違うのかという事を,仕事の仕方の違いを通してまとめてみました。
出典は明らかでありませんが,備忘録に残して,読み返す言葉です。
【考え方の違い】《忙しい人》は,「忙しい」と周りに言えば,「カッコイイ,頑張っている」と他人が評価してくれると思っている。**************
《仕事ができる人》は,「忙しい」と周りにに言うことは,「無能の証明」だと思っている。
【スケジュール】《忙しい人》は,終了時間への認識が甘い。(なんとなく終わったらいいな~的な)
《仕事ができる人》は,絶対にここまでに終わらせるというスケジュール意識が強い。
【納期・締切意識】《忙しい人》は,納期意識がギリギリ。(納期寸前で作業にとりかかるので,その仕事のみに集中してしまう為に効率が悪い。)
《仕事ができる人》は,前倒し。(納期より随分前から作業に取りかかるので,2つ以上の仕事を同時並行処理したりする効率の良い仕事の仕方ができる。)
【危機対応・リスクヘッジ】《忙しい人》は,せっかくスケジュールを作っても,緊急事態・トラブルで乱れっぱなし。
《仕事ができる人》は,緊急事態・トラブルでスケジュールが乱される事がほとんどない。
【タスクマネジメント】《忙しい人》は,いきなり仕事にとりかかって仕事にとりかかり,後で段取りを考える。仕事完了に近くなった時点で「仕事の目的と最終完成物」を考える。
《仕事ができる人》は,仕事の始めに「仕事の目的と最終完成物」を明確にし,感性の為の段取りを考えてて仕事にとりかかる。
【プライベートな時間】《忙しい人》は,「プライベートの時間を,とれたらいいな」的にしか考えていない。
《仕事ができる人》は,「プライベートの時間は絶対にとる」と最優先的に考え,その時間をホントに大切にする。
【期待値コントロール】《忙しい人》は,相手の期待よりちょっと低い仕事を行い,手直しで時間をとられる。その為に誉められる事も少なく,モチベーションも上がらない。
《仕事ができる人》は,相手の期待を少し上回る形の仕事を行うので,手直しがほとんどない。そのためお客様や上司から誉められる事も多く,モチベーションもアップしていく。
【最適化】《忙しい人》は,ホントはやらなくてよい仕事をたくさん抱えている。断るという事が苦手。
《仕事ができる人》は,自分しかできない仕事が中心。頼まれた仕事を断る事ができる。
【段取り】《忙しい人》は,段取りの時間を短時間で済まそうと考え,仕事にとりかかって段取りを考える。
《仕事ができる人》は,段取りを考える時間を十二分にとって,仕事にとりかかる。
【自己把握】《忙しい人》は,自分の性格的特徴を無視し,弱点ばかりが際立つような仕事ぶりをする。結果,成果の上がらぬ努力の時間と叱られる時間ばかりが増えていく。
《仕事ができる人》は,自分の性格を熟知し,強みを最大限発揮し,弱みが目立たぬような仕事をするから早く結果の出る仕事ができる。
【根回し】《忙しい人》は,根回しがヘタ。仕事が完成した後に,関係者から異議がでて,トラブルシューティングに奔走する。
《仕事ができる人》は,根回し上手。仕事を始める前に,重要な関係者をリストアップし,根回しを完了させる。仕事完了後に関係者からの異論はほとんど出ない。
【優先順位付け】《忙しい人》の優先順位は,納期期限が中心。納期が迫っているモノが優先順位が高い仕事になっている。
《仕事ができる人》の優先順位は,仕事の効率とその仕事の目標への寄与・貢献度。
【環境づくり】《忙しい人》は,集中できる環境を作る事ができない。電話や誰かが話しかけてきて作業の邪魔をする為に,同じ事を何度も考えないといけない。
《仕事ができる人》は集中できる環境を作る事ができる。誰も思考や作業を邪魔しない環境を作る事ができる。
【情報共有】《忙しい人》は,携帯電話にかける数より,かかってくる本数が多い。
《仕事ができる人》は,携帯電話にかける数の方が多い。携帯電話にかかってきて仕事を中断させられる事態を,先手を打つ事で防いでいる。
【リスク回避】《忙しい人》は,自分が他人に頼んだ事を忘れている。頼んだ相手も,頼まれた仕事を忘れており,それがトラブルを生み出す。
《仕事ができる人》は,自分が他人に頼んだ仕事は決して忘れない。時折,チェックも入れるので,相手も忘れることができない。
【コミュニケーション】《忙しい人》は,他人に事を頼むのがヘタ。依頼する際の打合せがヘタな為に,完成物を自分で手直しするのに時間がとられる。(人に頼まずに,自分でやった方が速いといった事になる)
《仕事ができる人》は,他人に事を頼むのが上手。依頼する際の打合せで詳細にイメージ合わせをする為に,完成物の手直しなどがほとんど発生しない。
【学習意欲】《忙しい人》は,学習する時間をとれていない。いつまでも同じやり方で仕事をしている。
《仕事ができる人》は,どんなに忙しい時でも学習時間の確保を行っている。学んだ知識をもとに,もっと効率的な仕事のやり方を求めて,いつもチャレンジをしている。
【効率化】《忙しい人》は,同じような仕事でも,イチイチ考えながら仕事をしている。
《仕事ができる人》は,同じような仕事が発生したら,考える事なく,仕事ができる仕組みを作り上げている。
【モチベーション管理】《忙しい人》は,運動などにも時間がとれなかったり,睡眠不足で仕事をしてしまう。時には徹夜も。そのため体調不良をおこしたり,身体に無理して仕事をしてしまう。それが原因のミスも生まれたりしてしまう。体調によりモチベーションも不安定になる。
《仕事ができる人》は,適切な運動を定期的に行い,十分な睡眠をとり仕事を行う。体調不良によるミス,集中力欠如によるミスは少なく,常に安定したモチベーションを維持している。
【自己管理】《忙しい人》は,「忙しい状態」を甘んじて受け入れてしまっている。
《仕事ができる人》は,「忙しい状態」事は絶対にイヤ。受け入れる事ができないと思っている。
メモしたころ,「仕事ができない自分」に喝を入れるように,《仕事ができる人》を目指そうとしていたようです。
ところで,「忙しい人」「仕事ができる人」を,別のものに置き換えたら…
2018年02月13日
言葉遊び。「V.S.O.P.」から「OLD」へ
 風の強く吹き,流れ落ちる水が,風に乗って水飛沫となって飛んでくるような日でした。
風の強く吹き,流れ落ちる水が,風に乗って水飛沫となって飛んでくるような日でした。日差しに暖かさを感じますが,寒い一日でした。
以前読んだ冊子に『「V.S.O.P.」から「OLD」へ』と題した記事がありました。
最近は,「V.S.O.P.」とか「OLD」と言っても,「それって何?」という方が多いような気がしますが,“たとえ”が伝わらなければ,あまり価値はないかな。
記事では,「学校はV.S.O.P.だ!」と学校を皮肉った言葉があると紹介していました。
「ベリー,スペシャル,ワン,パターン」だそうです。
それに対して,「OLDの授業を続けよう」と考えたそうです。
「オリジナル,ロング,ドラマ」の授業がうまくいくと,子どもの心のなかで,そのドラマが終わることなく,授業の終わった後も展開し続けるだろうというのです。
先生,いかがですか。
ついでに,4月から特別の教科となる「道徳」については,
○ どう説くと。
○ どう解く
○ どう溶く
○ 「どう得」にしていくか
いかがでしょう。
言葉遊びで内容を伝えていました。考えることが楽しくなりそうです。
そういえば,ある企業の方が「会社が求める人間像」をV.S.O.P.で語っていました。
そのV.S.O.P.は,
V.は,Vitality。「やる気」「体力」だそうです。
S.は,Speciality。「専門性」
O.は,0originality。「独創性」
P.は,Personality。「人間性」
例えをうまく使うと,相手に「なるほど」と思わせますね。
笑顔で,よい話を,楽しく伝えなくては…。
2018年02月12日
『ヨーコさんの“言葉” わけがわからん』(佐野洋子・文/北村裕花・絵)
 「再び寒気が…。積雪が…。」と予報されており,朝,心配して外を見ました。
「再び寒気が…。積雪が…。」と予報されており,朝,心配して外を見ました。白くはなっていますが,わずかでした。
気温が低く細かな雪で,強い風が吹き飛ばしたようです。
日中も,雪が舞ったり日がさしたりした寒い一日でした。
表紙に小さなチョウに向かっていく猫が大きく描かれた『ヨーコさんの“言葉” わけがわからん』(講談社・刊)
ネコを「可愛い」と言う方が多いですが,どうも苦手です。写真や絵も避けてしまいます。本書の表紙だけでなく,中にも何回か出てきますが,あまり気にせず読んでしまいました。
『100万回生きたねこ
大好評! NHKの人気番組「ヨーコさんの“言葉”」ついに第3弾刊行!シリーズになっているようで,本書が第3弾とのことでした。
300万部突破,大ベストセラー絵本『100万回生きたねこ』の著者,佐野洋子さんによるエッセイは,痛快で心を貫く言葉であふれています。ヨーコさんの世界観にぴったりだと大好評の北村裕花さんの250点近いイラストも,オールカラーで収録。
「ヨーコさんの言葉」に笑わされ,考えさせられ,また笑ったり…
ヨーコさんと楽しく。ご一緒に!
読書メモ
「その3 カラオケセットと井戸端会議」
〇定年になった男が 女にうとましがられるのは,言葉を失うからである。
男も下らない世間話でも,家庭の事情でも心を割ってお話しした方がよいのではないか。
他者との関係をもっと地をさらけ出して恥を捨てて言葉によって持った方がよいと,私は思うのよ。
ジイサンバアサンになってから人生の三分の一があるかも知れないのである。
だから下らない無駄話が出来る男は貴重である。
「その4 お月さま」
〇山道を車で走っている時 月を見ると,
昔のお姫様が月を見て 男を待っている事を想像する。
唐土で。日本の月を恋しがる男の孤独を考える。
十二歳くらいの子守女が,冬の月を指さしているひび割れた手を切なく思ったりして,
月は限りなく過去に私を連れてゆく。
あれは見るものである。全ての人類が月を見てあれこれ思いにふけったり,ただボーっとしていたのだ。
「その8 わけがわからん」
〇五十過ぎて仲良くなった夫婦は,けろうがたたこうが,びくともしなくなる。
愛という日本語にしてなじみにくいことばを超えるのである。
幾分かの憎しみを含んでも,その憎しみこそが,情を強くする。
実にわけがわからん。夫婦はわけがわからんのが いいのである。
「その9 二〇〇八年冬」
〇死ぬとわかるのは,自由の獲得と同じだと思う。
(略)
でも思う。私は死ぬのは平気だけど,親しい好きな友達には絶対に死んで欲しくない。
死の意味は 自分の死ではなく 他人の死なのだ。
人はいい気なものだ。
思い出すと恥ずかしくて 生きてもいられない 失敗の固まりのような私でも
「私の一生は いい人生だった」と思える。
もくじ
その1 神の手
その2 言葉
その3 カラオケセットと井戸端会議
その4 お月さま
その5 うるさいわね
その6 私はどちらも選べなかった
その7 真二つの結婚
その8 わけがわからん
その9 二〇〇八年冬
【関連】
◇ヨーコさんの“言葉”(NHK)
◇Yuka Kitamura Illustration
タグ :読書
2018年02月11日
建国記念の日
 午前中,曇り空でわずかに雪も舞いました。午後になって青空が見えてきましたが,強い風が吹いて寒い日でした。
午前中,曇り空でわずかに雪も舞いました。午後になって青空が見えてきましたが,強い風が吹いて寒い日でした。今日は,国民の祝日の一つ「建国記念の日」でした。
1966(昭和41)に「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として定められました。
もともとは,日本の初代天皇である神武天皇が即位された紀元前660年2月11日を「紀元節」として,1873(明治5)年から1948(昭和23)年まで“祭日”にしていましたが,戦後,GHQが皇室と神道の関係が深いなどの理由から,祭日を廃止しました。
この「紀元節」だった日であり,論議のある(?)祝日の一つです。記念日でなく“記念の日”としたのも,その配慮でしょう。
「建国記念日」であれば,文字通り「建国を記念する日」です。
“記念日”は,歴史的事実として日付が確定している日を記念するという意味です。
“記念の日”は,日付は確定していないけれど,そのことを記念する日という意味になります。
アメリカの建国記念日は「独立記念日」で,7月4日です。これは,1776年の大陸会議でアメリカ独立宣言に署名がされた日です。
スイスの建国記念日は8月1日,オーストリアは10月26日,それぞれ歴史的事実を元にしています。
しかし,日本には「この日に建国された」「この日に独立した」といった確定した日が見つかりません。
いろいろな考えがあり,祝日「建国記念の日」となるまでには,紆余曲折があったようです。
さて,みなさんの「建国記念の日」は,いかがでしたか。
2018年02月10日
オリンピック。『心をとめて 森を歩く』(小西貴士・写真・言葉/河邉 貴子・文)
 天気予報通りに“暖かい日”になりました。
天気予報通りに“暖かい日”になりました。気温の低い朝でしたが,ここ数日では少し“まし”でした。曇り空で日差しはありませんが,少しずつ気温が上がり,日陰に積もっていた雪が溶けだしていました。
週明けに再び寒くなるようですが,ここまま“暖か~い春”に向かっていってくれるとよいのですが…。
ピョンチャンオリンピック(第23回冬季オリンピック競技平昌大会)が始まりました。昨夜のテレビでは,開会式が中継されていました。
「映像を見るのはテレビ」という方が多いでしょうが,「オリンピックを観る」には,いろいろな方法(メディア)があります。
今日,休憩時間に観たのは,ネットの動画です。フィギアスケートの宇野選手の演技は,結果しか知らなかったのですが,最初から最後まで見ることができました。また,開会式のハイライトも,いろいろな編集のものを観られるようです。
今日観たのは,NHKと民放のサイトです。
◇NHKピョンチャンオリンピック
◇gorin.jp 民放オリンピック公式動画サイト
映像は「ライブ,ハイライト,見逃し」「ライブ,動画・ピックアップ」と,見たいものが見られるようになっています。
以前,駅伝中継を話題にしましたが,テレビ放送では見ることのできない場面や競技を選んで観ることができるネット動画(中継)は,スポーツ観戦の楽しみ方を変えているように思います。
みなさんは,ピョンチャンオリンピックの競技を観ますか。
どんな方法,場所で観ますか。
虫食いの葉,そこに水の玉が目立つ表紙の『心をとめて 森を歩く』(フレーベル館・刊)
「森に心をとめてきた人と子どもに心をとめてきた人。ふたりが織りなす珠玉のフォト&エッセイ。」と紹介される本書は,写真家・森の案内人の小西氏の「写真とことば」29編,その間に教育研究家の河邉氏の「エッセイ」6編で構成されています。
ハサミムシの写真には,
ノハラアザミのお花からの言葉がありました。
お尻を つき出して
ハサミムシが
LOVE&PEACE!
と
笑いました
写真を改めて見ると,虫の姿が“ピース”を出してLOVEとPEACEを伝えているように思えてきます。楽しくなってきます。
河邉氏の最初の「心をとめる」を
「心をとめる」とは,どういうことだろうか。と語り始め,
何かに心をとめようとするとき,そこには,とめようとする「意志」が働いているように思う。
「意志」という言葉が強すぎるならば,(略)
心をとめるということは,心をとめようと思った対象が,ひそやかにもっている物語を想像し,そのものがもっている意味を見逃さない行いといえるのかもしれない。そんな風にして,森でも街でもどこでも歩けたら,気持ちがちょっと楽しくなる。と,本書のタイトルにつながる話をしています。
“小さなもの”にゆっくりと目と耳を向けると,そこに広がっている“大きな世界”に驚かされます。ときどき開いて,語りを聴き直したい一冊です。
読書メモ
耕した土に芽吹くもの
耕さずとも芽吹くもの
孑いた種から芽吹くもの
孑いた覚えなく芽吹くもの
愛おしさは同じように
どこの荒れ地に芽吹こうとも
心の真ん中で抱きしめる
「心をとめてもらうこと」
子どものことをあまり理解していない人は,子どもというものは自己中心的な思考の持ち主と思っているかもしれないが,それは誤解である。自然の変化に敏感なように,周りの人の状態の変化によく気づく。
(略)
誰かに心をとめてもらえることは,こんなにも温かく,嬉しいものなのだ。
私は目には見えない大切なものに,心をとめて歩いてきたかな。少し軽くなった心のままにトモコちゃんの隣でブランコに揺れながら,これからは,どんなときにも,ていねいに歩けるようになろうと思った。
目次
写真とことば 小西貴士
序
うれしい日
LOVE&PEACE
芽吹きのささやき ほか
文 河邉 貴子
心をとめる
心の可動域
心がとまる
豊かな心はどこから… ほか
【関連】
◇NHKピョンチャンオリンピック
◇gorin.jp 民放オリンピック公式動画サイト
◇Olympics | Olympic Games, Medals, Results, News(IOC 国際オリンピック委員会)
◇第23回オリンピック冬季競技大会(2018/平昌)(JOC 日本オリンピック委員会)
◇2018平昌冬季オリンピック及び冬季パラリンピック大会
2018年02月09日
「忍耐と意思」(青春10)。
 今朝も厳しく冷え込みました。
今朝も厳しく冷え込みました。しかし,晴れの日で,日中は気温が上がり暖かくなりました。
草花が,いつ芽を出そうか待ちわびているような気がします。
春近し! もう少し。
『しんしろ青春の会』の10回目。2003(平成15)年1月は,「忍耐と意思」(サムエル ウルマン)を載せています。この詩は,これまでも1月や2月に紹介されることの多いものです。
「忍耐と意思」(サムエル ウルマン)寒い冬が続くなか,新年となり「次へ向かう」「新たに始める」「これから」を考える頃,「我が心舞いあがれ 輝きあれ」に力を込めていたようです。
鳥は春を待ち
花冠はいそしみ
蜘蛛はうずくまり
野の鶏はつまさき立ち
さざなみ重なり小川は流れ
らくだ たっぷり水を飲み
思い ゆっくり形を作る
逆まく嵐を勇気はしのぐ
力強き魂への試練
傷つけど たじろかず
すべては大なる終曲に記され
我が心舞いあがれ 輝きあれ
みなさんの心は舞い上がり輝いていますか。
裏面には,市内の話題が載り,そのなかに「魚」のことがありました。
「ジンタ(ゴリ)」 … 学名はヨシノボリ最近,「ジンタ(ゴリ・ヨシノボリ)」を見たり獲ったり,話をしたりしておらず,今もたくさんいるのか承知していませんが,地域の自然のなかで元気に生息しているものと思います。
市内に流れる小川やそこから流れ出る豊川などに行くと,いつも足もとまで近寄ってくる大変愛くるしい姿をした魚です。
この魚,近ごろ数が減ってきたのか,以前ほど見かけなくなりました。北陸の方では,ゴリ料月とかゴリの佃煮などに使用し減っていると聞いでいますが,こちらではどうでしょうか。
しかし,このジンタ…東郷東小学校付近の川には今でもたくさんいるようです。この地方は,このようにまだまだ貴重な魚が保護されていることは素晴らしいことだと思います。

小学生向けの「わたしたちの新城 自然編」には,この他にも,当地の自然のなかで見られる生き物が紹介されています。
みなさん,最近,地域の生き物を見て(観察して)いますか。
【関連】
◇わたしたちの新城 自然編
【参考 タグ;青春の会】
◇2017/10/07 新米。「アカウンタビリティー」(青春9)。
◇2017/09/23 秋分の日。蜂と虫と。(青春8)
◇2017/09/20 「仕事は“はたおり”」(青春7)
◇2017/09/14 「義務 Duty」(青春6)。部活動。
◇2017/09/12 「波を起こす」(青春5)
◇2017/09/07 「どうってことない」(青春4)
◇2017/08/31 「こつこつとこまめに」(青春3)
◇2017/08/25 「GROWING APACE」(青春2)
◇2017/08/22 記録「しんしろ青春の会」
タグ :青春の会