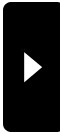2025年02月28日
6-09 南部地区の古石塔(2) (作手村誌57)
 『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。
『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。城址に続き、作手地区に残る古石塔についての記録です。
現在では、記事にある状況とは変わってしまっている場所もありますが、石塔が建てられた当時の“想い”や“願い”を感じながら、作手の歴史を辿っていきたいと思います。
********
第二編 歴史 - 第二章 中世
第十節 古石塔
(つづき)
*南部地区の古石塔
〔和田出雲守墓〕 大字保永字エマツ(山林) (図35)
佐宗候計宅裏に2基の宝篋印塔があり、双方の間に「出雲明神」と記された石碑が祭祀されている。出雲明神というのは奥平貞俊の二男貞盛で、貞盛が出雲守貞盛と称したところから、後世、石碑の建立に際し、「出雲明神」と記されたものである。この出雲守貞盛は最初岩波に居住したが、1537(天文6)年石橋館の戦で、亀山城主奥平貞勝を援け、その功により和田城主となった武将である。宝篋印塔は建立以来幾星霜も経過しているにもかかわらず、損傷はほとんどなく、往時の姿をそのまま伝えているかのようで、村内の宝篋印塔のうちでは、保存状態の良い方である。
 ○ 宝篋印塔(2基) いずれも砂岩製で、推定年代は向って右側が室町時代中期、左側が室町時代後期である。右側のものは残念なことに塔身がない。それ以外は損傷が無く保存状態が良い。この塔身の欠落は、このものに限らず村内各所で顕著に見られる。どうしてであろうか。
○ 宝篋印塔(2基) いずれも砂岩製で、推定年代は向って右側が室町時代中期、左側が室町時代後期である。右側のものは残念なことに塔身がない。それ以外は損傷が無く保存状態が良い。この塔身の欠落は、このものに限らず村内各所で顕著に見られる。どうしてであろうか。総高は70cmで、基礎19cm×23.8cm、笠14cm×26.3cm、相輪37cm×12cmである。
左側のものも右側同様に塔身が無い。そのうえ相輪の宝珠部分が欠落しており、右側に比較して総体的に小柄である。
総高は51cm、基礎17cm×19.2cm、笠11cm×24.5cm、相輪23cm×11cm
○ 出雲明神祠(1基) 砂岩製で江戸時代中期以降と推定される。全体的にしっかりしているが、前の柱二本が紛失している。
総高は4.8cm、基礎10cm×20.5cm、祠の総高38cm、屋がい幅25cmである。
〔黒谷久助墓〕 大字高松字松葉沢30番(山林) (図32)
この墓所について、『旧作手村誌』には、「大字高松北赤羽根黒谷源造氏の宅地の地端山林に…」とあるが、現在は同地には無く、字松葉沢のものを、その墓と称し、松尾大明神として祀っている。久助は奥平氏に仕官として、1573(天正元)年8月21日の打木の戦いで武田勢と激戦の末戦死した。
 禅源寺過去帳に、「白峰道圭信士 奥平仕官黒谷久介 天正元年八月二十二日」とあり、戦闘の翌日亡くなったことになっている。宝篋印塔、一石五輪塔が馬頭観音などとともに祀られている。
禅源寺過去帳に、「白峰道圭信士 奥平仕官黒谷久介 天正元年八月二十二日」とあり、戦闘の翌日亡くなったことになっている。宝篋印塔、一石五輪塔が馬頭観音などとともに祀られている。○ 宝篋印塔(3基) 室町時代中期末と江戸初期のもので砂岩製。3基いずれも完全なものは無い。
総高50cm、基礎21cm×21cm、塔身は無く、笠14cm×26cm、相輪も無く、宝珠15cm×10cmである。他は省略。
○ 一石五輪塔(3基) 砂岩製の室町後期と推定されるもので、2基は完全だがいずれも粗雑である。
全高51cm×幅20cmである。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「作手村誌57」〉で
注2)本文内で、縦書き漢数字で書かれている数値を横書きに改めて表記した箇所、年号に西暦を追記したところがあります。
注3)古石塔の所在記号が付されたものは、前項の分布図に表記されている箇所です。
《参考》
○ 古石塔とは、古くからある石造りの仏塔や石の塔を指します。
○ 石塔の種類?
層塔、宝塔、宝篋印塔、五輪塔、板碑、笠塔婆、無縫塔、石幢 など
○ 石塔の建立目的
仏塔は、仏教の開祖であるお釈迦様のお骨である舎利を納め供養する建物であるストゥーパ(サンスクリット語)に由来するといわれてます。
タグ :作手村誌57
2025年02月27日
6-08 南部地区の古石塔(1) (作手村誌57)
 『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。
『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。城址に続き、作手地区に残る古石塔についての記録です。
現在では、記事にある状況とは変わってしまっている場所もありますが、石塔が建てられた当時の“想い”や“願い”を感じながら、作手の歴史を辿っていきたいと思います。
********
第二編 歴史 - 第二章 中世
第十節 古石塔
(つづき)
*南部地区の古石塔
〔菅沼主水墓〕 大宇大和田字内ノ沢(寺境内) (図41)
慶雲寺裏に高さ70cmの宝篋印塔がある。主水は菅沼定芳の五男定賞で、海老菅沼氏3,000石の初代であり、慶雲寺の開基である。
〔鈴木金七郎重正祠〕 大字田代字大田代 (図38)
金七郎は設楽郡川上村(新城市)の生まれで、1575(天正3)年5月14日夜半、武田勝頼の軍に包囲され、籠城の長篠城から織田・徳川の援軍を求めて脱出した鳥居強右衛門勝商に次いで、同18日深夜脱出に成功、翌19日弾正山の家康に来援を謝し、城は堅固である旨上意を伝え帰城しようとしたが、家康の言に従い在陣し、合戦後一旦川上村に引き戻り、のちに作手の大田代に閑居して農業を営み田代鈴木氏の始祖となった。
○ 祠(2基) 花崗岩製で、右に「金七郎」、左に「同室」の祠が有る。金七郎の屋蓋には下り藤の家紋が、また室の屋蓋には菱カタバミの紋が有る。これも江戸時代初期末の作と推定される。
金七郎墓の総高は、160cm、台座10cm×53cm、塔身42cm×36cm、屋蓋23cm×58cm、宝珠26cm×13cmである。
台座10cmは、50cmのコンクリート製基壇に塗り込められた上に出ている。塔身前部の右側に「鈴木金七郎重正」、中央に「三州設楽郡田代村」と読める。また左側面は右側面同様の字のように見えるが判然としない。
室墓の総高は、115cm、台座10cm×56cm、塔身38cmっける43cm×35cm、屋蓋42cm×61cm、宝珠25cm×12cmである。
これにも右側に「鈴木」の文字が読めるがその他は判読不可能である。屋蓋は金七郎のものに比較して角張り、反りが少ない。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「作手村誌57」〉で
注2)本文内で、縦書き漢数字で書かれている数値を横書きに改めて表記した箇所、年号に西暦を追記したところがあります。
注3)古石塔の所在記号が付されたものは、前項の分布図に表記されている箇所です。
《参考》
○ 古石塔とは、古くからある石造りの仏塔や石の塔を指します。
○ 石塔の種類?
層塔、宝塔、宝篋印塔、五輪塔、板碑、笠塔婆、無縫塔、石幢 など
○ 石塔の建立目的
仏塔は、仏教の開祖であるお釈迦様のお骨である舎利を納め供養する建物であるストゥーパ(サンスクリット語)に由来するといわれてます。
タグ :作手村誌57
2025年02月26日
歴史から考えた(2.26事件、二〇三高地)
 2025年は、年末(12/25)に”昭和100年”となり、夏(8/15)に"戦後80年”を迎えます。
2025年は、年末(12/25)に”昭和100年”となり、夏(8/15)に"戦後80年”を迎えます。また、昭和40年に生まれた方が60歳の還暦を迎える年です。
“人生100年時代”と呼ばれて久しい今、還暦を話題にするのは相応しくないかもしれませんが、2025年に「100、80、60、40」と並ぶ数字に、意味があるように思います。
それは、次への“起点”であり、新しい“出発点”となるもの(年・数)です。
1936(昭和11)年の今日、ニ・二六事件が起こりました。
4年前(1932/05/15)の五・一五事件に続いて、軍隊の将校達が起こした反乱です。
それぞれ反乱は鎮圧され、失敗でしたが、政党政治が終わり軍国主義が台頭していきました。
歴史の節目となった出来事です。
明治時代に起こした日露戦争(1904年2月~1905年9月)があります。
ロシアの朝鮮進出をくいとめ、自国の独立と安全を守るために戦った…。
NHKスペシャルドラマ 坂の上の雲で二〇三高地が描かれていました。旅順攻囲戦では最大の激戦地となった場所です。
圧倒的に不利な状況で“死闘”の末、二〇三高地を陥落させました。勝利…。
もし、この戦いに敗けていたら、その後の日本、昭和は別のものになっていた…。
勝利を喜び、意味のある戦い(日露戦争)と指導者はいうでしょう。しかし、その勝利は数多くの「歩兵・兵の犠牲」によって為しえたものです。ドラマのなかでも、そのことが出てきます。
さらに、この戦いで“小が大に挑む愚かさ”を学んだはずなのに、昭和に“同じ節目”を作ってしまいます。
5.15、2.26 も、その節目になってしまいました。
よい戦争や意味のある戦争はありません。
勝利は、犠牲になった人の元には届きません。
戦争は、起こしてはいけないのです。
誤った節目を生まないよう、歴史を知り・学び、考え、行動したい。
世の中、「良い人ばかりだから、争い(戦争)が起こる」のです。だって「自分は悪くない。悪いのは相手」だそうです。
悪い人が攻撃されるのは当然…。
本当ですか。
「悪いのは私」という“悪い人ばかり”になったら、争い(戦争)は起こらないでしょう。
すべての戦争、紛争の犠牲者に 合掌
【関連】
◇戦後80年/昭和百年(読売新聞)
◇プレイバック 昭和100年(産経新聞)
◇昭和100年祭 | 昭和200年に向けたカルチャー創造宣言
2025年02月25日
【備忘録】「学校規模の適正化」から考える
 日本社会の“少子化”が進み、さまざまな場所で「子供の数が少なくなって、今までのようには…」、「地域の活力がなくなってきて…」など話題に出てきます。
日本社会の“少子化”が進み、さまざまな場所で「子供の数が少なくなって、今までのようには…」、「地域の活力がなくなってきて…」など話題に出てきます。少子化の進展は、多くの地域で“小規模校の増加”として表れています。
昨年の夏、文部科学省から「令和5年度 学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」の結果が発表され、域内に小規模校があると回答した市町村が8割以上でした。
そうした小規模校を対象に“学校統合”を進めて、「学校規模の適正化」を図っていきます。
しかし、それが進められない場合が増えているそうです。
学校間の距離が遠過ぎる、すでに自治体で1校となっているなど、過小規模の学校があっても「統合の対象となり得る学校がない」という自治体が11%ありました。
“適正な”学校規模とは…
小規模校1校の自治体は…
“トヨタ”のある豊田市でも、少子化への対応が急がれているようです。
豊田市内の一部の小学校で、児童数の減少が顕著になってきている。市教委の調査では、全校児童数30人以下の小学校が現在の8校から2030年度には20校と倍以上に増えると予測されている。児童数も現在の約2万2千人から同年度には約1万8千人に減る見込み。(略)◇学校再編、しこり避けて 豊田市議会9月定例会…(中日新聞Web)
「児童への対応は、質的、量的な面で難しくなっている」。2日の一般質問で、市教委の山本浩司教育長はこう答弁した。(略)
市教委が08年に定めた「学校規模の適正化に関する基本方針」では、12学級以上24学級以下を推奨し、選択肢の一つに「地域合意を前提とした統廃合」を挙げている。この方針により10年には藤沢小、12年には築羽小が、適正規模を外れ、改善の見込みがないとして統廃合に至った。本年度はこの方針が改定される予定だが「小規模校への対応として、ベースとなる部分は変わらない」と(略)
ただ、具体的な適正化の方向性については検討中。岩月課長は「通学距離や地域の状況なども踏まえる必要があり、すぐに統廃合の議論に入るわけではない」と語る。
少子化が進む中、全国各地で学校再編が進められている。記者(25)が通った都内の母校でもかつて、統廃合の議論が巻き起こった。校舎はどこに置くのか。伝統や地域の輪はどう維持するのか。議論は紛糾し、保護者や子ども、地域間の溝を深めた。統廃合は避けられたが、そのしこりを感じることは今でもある。そうならないためにも、地域や行政は現実を冷静に見つめ、時間をかけて準備していってほしいと願う。
子供は、どのような規模を“適正”だとするのだろう…
学校には、“リアル”も“バーチャル”もありそうだが…
50年後、100年後の日本社会に生きる「学校」って何だろう…
【参考】
◇Facebook投稿 2024/08/02
◇東愛知新聞 2023/11/15 記事
【 #新城市 】こども園統廃合視野に、小学校再編へ
— 【公式】東愛知新聞Web@豊橋・豊川・蒲郡・田原・奥三河 (@Higasiaichinews) November 14, 2023
13日・市役所
新城市の第2回総合教育会議が開かれ、小学校の再配置について協議しました。
安形博教育長
「統廃合など何らかの選択が迫られている時期にある」
▼記事はこちらhttps://t.co/mFzUkP1UR1#東愛知新聞 #教育委員会 #地域情報
2025年02月24日
『秘色の契り 阿波宝暦明和の変 顛末譚』(木下昌輝・著)
 第172回直木三十五賞の候補となった『秘色の契り 阿波宝暦明和の変 顛末譚』(徳間書店・刊)を読みました。
第172回直木三十五賞の候補となった『秘色の契り 阿波宝暦明和の変 顛末譚』(徳間書店・刊)を読みました。江戸時代、こんなにややこしい殿様は他にいなかったかもしれない。
小藩から25万石の大藩に養子入りし、苛烈な藩政改革に取り組んだ。
誰にも負けぬ弁舌と知識、厳しい倹約令と公共投資の両立、当時の身分制度を破壊する新法、そして、どこにもない市を生み出そうとしたが……
蜂須賀重喜という男が愚者なのか賢者なのか、勝者なのか敗者なのか。
皆様の目で確かめてください。
三十万両もの巨額の借財を抱える徳島藩。藩政改革を担ったのは、型破りな人物だった。
徳島藩蜂須賀家の物頭、柏木忠兵衛は新藩主候補との面会のため、江戸に急いだ。藩の財政はひっ迫している。新たなまとめ役が必要だった。
しかし―。「政には興味なし」新藩主となった蜂須賀重喜はそう言い放つ!家老たちの専横に抗して、藩主の直仕置による藩政改革をめざす忠兵衛ら中堅家臣団。対立が激化するなか、新藩主が打ち出した驚きの改革案とは!?そして、徳島藩を狙う大がかりな陰謀とは…。
アクション&サスペンス満載、著者渾身の時代長篇!
題名の「秘色」に、表紙にも背にもフリガナが付いていましたが、それに気づかず「ひしょく」と思い込んでいました。
“ナゾの色”あるいは“ヒミツ”が縁を結んでいくのだろうと予想しながら、本を開きました。
目次に続いて、見開きで「秘色の契り 人物表」がありました。このような人物表や相関図の載る物語は、「これは誰だっけ?」と何度も見直すことになるので、早速コピーをして、すぐ確認できるようにしました。
 複雑な人間関係ではありませんが、コピーのおかげで読みやすかったです。
複雑な人間関係ではありませんが、コピーのおかげで読みやすかったです。人物表の最初に載るのは、阿波国徳島藩第十代藩主 蜂須賀重喜です。実在の人物で、徳島藩四羽鴉と呼ばれた柏木忠兵衛、樋口蔵之介、林藤九郎、寺沢式部が、徳島藩の復興を期して佐竹家分家新田藩から迎えました。
巨大な借財にあえぐ徳島藩は、お飾りの藩主を据えて五大老が牛耳っており、徳島藩の特産物「藍」を作る職人が、大阪商人の餌食になっていました。
その商人が、表紙に描かれていた人物のようで、新しい藩主候補を探しに向かう忠兵衛が(最初に)船で出会った金國屋の金蔵です。
商人が武家を使うというのか、この男のいう話が、全く理解できない。このときの忠兵衛には不思議な話でしたが、物語の後半で…。
「下手すりゃ、この国もえげれすの商人に食われるかもしれまへんで」
「この国?」と、忠兵衛は復唱した。
「ええ、さいだす」
藩主になりたくなかった重喜ですが、第十代藩主となってからは“新しい法度”により藩政改革を一気に進めようとします。
一体、幾度目の休息であろうか。もう柏木忠兵衛にも分からない。二日前の昼から始まった衆議は、波乱がつづいた。三塁の制という忠兵衛らさえ聞いたことがない法度は、改革に賛成だった家臣たちでさえ反対に回るほどだった。夜を徹した衆議は、翌日になっても終わらず(略)混乱の続く徳島藩の改革は進むのか…。
「秘色(ひそく)」は、藍染めから生まれる特別な色を指し、物語の重要なテーマです。
その「秘色(ひそく)の契り」は…。
徳島藩の「藍」は…。
本書は物語で、史実とは異なる部分もあるでしょうが、“蜂須賀重喜の行った再興(改革)”が、現代の日本経済、日本社会に求められている気がしました。
どこかに隠れている“現代の重喜と四羽鴉”を見つけ出すときではないでしょうか。
映画化、ドラマ化が楽しみな作品でした。お薦めの物語です。
目次
一章 末期養子
二章 五社宮一揆
三章 船出
四章 明君か暗君か
五章 蝿取り
六章 呪詛
七章 謀略
八章 密約
九章 藍方役所
十章 血の契り
十一章 主君押し込め
十二章 空の色
【関連】
◇木下昌輝@歴史エッセイ本4月発売!! (@musketeers10)( X )
◇直木三十五賞(公益財団法人日本文学振興会)
◇とくしまヒストリー ~第22回~(徳島市公式ウェブサイト)
タグ :読書
2025年02月23日
天皇誕生日。 地区総会。 『保健室には魔女が必要 MMMの息子』(石川宏千花・著)
 今日は、国民の祝日の一つ「天皇誕生日」です。
今日は、国民の祝日の一つ「天皇誕生日」です。そして、日本の「国家の日」「ナショナル・デー(National Day)」です。
昨日の午後、地区の総会(改選)がありました。
例年のように、本年度の活動、会計の報告があり、協議事項、議題の審議、次年度の組織など検討、決定しました。
高齢化の進む地域で、新たな“継承”があり、次への“勢い”が出るように提案があり、さまざまな視点や立場から声があり、長い協議となりました。
それぞれが“正しいこと”ですが、日ごとに高齢化していくなかで“持続可能な最適解を見出すのは難しいことです。
総会では、久しぶりに会う方もおり、いろいろな話をうかがえました。ありがとうございました。
子供達は、保健室の先生が好きです。ケガしたり、苦しくなったりしても、保健室で休んだらスッキリします。
“保健の先生”は、魔法使いなのでしょうか。
児童書コーナーにあった『保健室には魔女が必要 MMMの息子』(石川宏千花・著)を手に取りました。
主人公は、中学校の保健室の先生にして魔女。
考案する「おまじない」を流通させ、もっとも定着させた魔女が選ばれる七魔女決定戦に参加している。
魔女たちとの交流、魔女狩り団体MMMに関係する少年の出現、そして七魔女決定戦にも新たな展開が!
もろくて、かたくなな悩める中学生におくる連作短編集シリーズ、第2作。
今回の悩みは
★友だちばかりほめられるのが気になる
★将来の夢がない
★みんなとノリがあわない
★女の子らしい子になりたい
★だらだらしていると怒られる
★自分をみじめだと思ってしまう
それぞれの話は、
わたしは魔女だ。で始まります。
保健室の先生でもある。
魔法で何かを解決したり、何かを倒すことをするのではなく、日々「おまじない」を考案しています。
そのおまじないを、保健室に来る生徒に授けます。
悩める中学生たちの話に耳を傾け、時にはとっておきの“おまじない”を伝授する。なぜなら自らが考案する“おまじない”を流通させ、もっとも定着させた者が七魔女の最後のひとりに選ばれるから……。
一話が短く、短い時間で楽しめます。小学生の読み物としてぴったりです。
大人が読んでも楽しめます。
あなたも、みんちゃん先生の“おまじない”を聴きたくありませんか。
もくじ
ほめ上手になるおまじない
夢が見つかるおまじない
ノリがよくなるおまじない
女の子らしい子に なれるおまじない
だらだらしてても 怒られなくなるおまじない
自分をみじめだと 思わなくなるおまじない
【関連】
◇石川宏千花 (@hirochica_no)( X )
【おまけ:日経社歌コンテスト2025】
今年の「日経社歌コンテスト2025」の決勝が、2月27日(木)に開催されます。
大賞に輝くのは…。
◇日経社歌コンテスト(日本経済新聞)
◇日経社歌コンテスト (@shaka_contest)( X )
2025年02月22日
『笑う森』(萩原浩・著)
 帯に「5歳児が行方不明になった、生死不明の一週間、神森で、何が起きていたのか」の言葉が気になって手にした『笑う森』(新潮社・刊)です。
帯に「5歳児が行方不明になった、生死不明の一週間、神森で、何が起きていたのか」の言葉が気になって手にした『笑う森』(新潮社・刊)です。5歳の男児が神森で行方不明になった。
同じ一週間、4人の男女も森に迷い込んでいた。拭えない罪を背負う彼らの真実と贖罪。
原生林で5歳のASD児が行方不明になった。1週間後無事に保護されるが「クマさんが助けてくれた」と語るのみで全容を把握できない。バッシングに遭う母のため義弟が懸命に調査し、4人の男女と一緒にいたことは判明するが空白の時間は完全に埋まらない。
森での邂逅が導く未来とは。希望と再生に溢れた荻原ワールド真骨頂。
読み終えて、本書が“読書メーターOF THE YEAR2024”の一冊に選出されていたことを知りました。納得の一冊です。
表紙は暗い森が描かれ、大木の前に立つ子供、その大木に隠れるように題名が書かれています。
中表紙には、ミニカーの列が描かれています。このミニカーと表紙の子供は…。
物語は、「小樹海」とネットで呼ばれている神森で行方不明となった5歳の男児を、下森消防団団員の田村武志が探す場面から始まります。
行方不明から一週間が過ぎた11月19日、「合体樹」の根と根が交錯してできた空洞で、5歳児を武志が発見しました。
5歳児が一人で一週間を生き抜きました。奇跡です。
 行方不明になっていたのは、自閉症スペクトラム障害と診断されている山崎真人で、定型発達の子供と同じようなコミュニケーションを取ること、行動することが難しい子供です。
行方不明になっていたのは、自閉症スペクトラム障害と診断されている山崎真人で、定型発達の子供と同じようなコミュニケーションを取ること、行動することが難しい子供です。行方不明になった日…。
深夜、午前0時少し前に「本日の操作はここまでです」と告げられます…。
二日目…。
五日目…。
岬(母親)は些細な情報でも得たいと見ていたネットに、岬や真人に関する噂が…。
真人は、一週間過ぎて発見されたのに、衰弱はなく、食べ物を摂っていたようです。
何を食べていたの?“くまさん”とは何? 誰? …
「ごはん、しらないおかし」
誰にもらったの、と聞くと、
「くまさん」
神森に真人が行方不明になっていた一週間、神森に他の人、ものがいました。
死体を遺棄しにやって来た美那…
YouTubチャンネルでソロキャンプを配信している戸村拓馬…
組の上納金を盗み、逃走中の谷島…
神森を死場所と定めた畠山理実…
そして、森の…
彼らが、それぞれ真人と遭遇していました。
そのとき…。
真人の1週間、何があったのか。それを、母親の岬、叔父の冬也が追っていきます。そこにYouTuberの拓馬が加わり、明らかになったのは…。
子供の行方不明から始まり、殺人や暴力団、いじめ、自殺…と事件(?)が続きますが、登場人物の言葉や行動にくすっとし、純真な真人の言葉と行動そして成長に、心に優しい風が吹き込むような気持がしました。
厚い本ですが、その文量を気にせず読み切れる物語です。
みなさん、お薦めです。
【関連】
◇本好き”が選ぶ!文芸・小説 おすすめ本年間ランキング!読書メーターオブザイヤー2024-2025(読書メーター)
タグ :読書
2025年02月21日
6-07 中部地区の古石塔(6) (作手村誌57)
 『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。
『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。城址に続き、作手地区に残る古石塔についての記録です。
現在では、記事にある状況とは変わってしまっている場所もありますが、石塔が建てられた当時の“想い”や“願い”を感じながら、作手の歴史を辿っていきたいと思います。
********
第二編 歴史 - 第二章 中世
第十節 古石塔
(つづき)
*中部地区の古石塔
〔奥平家第二廟所〕 大字白鳥字小田前(山林) (図30)
加藤義孝宅裏山の中腹で、第一廟所との間を国道301号線が走っている。奥平家の室3人の改葬墓所と伝え、現在、積石五輪塔3基の脇に、稲荷大明神・彼岸神・地ノ神などの石祠がある。
 ○ 積石五輪塔(3基) この地域では比較的に珍らしい花崗岩製で、推定年代は室町後期である。このうち1基は風・空輪がそぐわず、また1基は風・空輪を欠く。そして他の1基も風・空輪を欠く上に火輪も残欠となっている。すべて小型であるが、そのうちから最初の1基の規模を示すと、
○ 積石五輪塔(3基) この地域では比較的に珍らしい花崗岩製で、推定年代は室町後期である。このうち1基は風・空輪がそぐわず、また1基は風・空輪を欠く。そして他の1基も風・空輪を欠く上に火輪も残欠となっている。すべて小型であるが、そのうちから最初の1基の規模を示すと、総高は48.2cmを測り、その各部は地輪14.2cm×16.2cm、水輪11cm×17cm、火輪8.7cm×14.8cm、風輪6.3cm×10.8cm、空輪8cm×12.2cmである。
〔奥平弾正祠〕 大字清岳字寺屋敷(墓地) (図22)
慈昌院境内に所在する寺墓地の中心にある。奥平弾正久勝は、亀山城主奥平貞久の二男で、亀山城の西300mほどの所に石橋の館を築き居住していた。(「慈昌院旧記」には、「久勝は貞久の弟」とある)1537(天文6)年9月21日、二代奥平弾正繁昌(戒名繁室慈昌大居士)は、亀山城主奥平貞勝を亡ぼそうとして察知され、一族の和田出雲の急襲を受け、弾正とその郎党45人が誅殺され、のちに里人が難を恐れ、館址に石橋山慈昌院を建立し、奥平弾正祠を建てた。
○ 祠(1基) 花崗岩製で、右側面に「天文六丁酉九月廿一日」とあり、左側面に「奥平弾正宮」とある。しかし、祠の石質・製法などから見て、江戸時代初期末の作と推定され、後世の建立であることは確かである。
総高は78cm、台座6.5cm×49cm×49cm、塔身33cm×37cm×33.5cm、屋蓋20cm×60cm、宝珠18cm×8.9cmである。
〔奥平出雲守墓〕 大字岩波字池田(山林) (図13)
岩波城主奥平貞寄の墓である。父は和田城主貞盛で、貞寄は1575(天正3)年の長篠合戦で籠城した将士の一人で、墓所は岩波の集落を300mほど下った川沿いの山林中にある。石塚の上に砂岩製の高さ30cmの祠に、「享保九年十月吉日」(1724)と刻され、出雲明神として里人が祀っている。
〔奥平貞久墓〕 大字清岳字六畑(山林) (図26)
亀山城址の東北すそにあり、二代亀山城主である。以前には数基の一石五輪塔があったが、現在は高さ47cmのもの2基しか見当たらない。里人は「六畑地蔵」と呼んでいる。
〔奥平貞久室墓〕 大字清岳字ココメ沢(塚) (図20)
一名姫塚と言われ、武士塚と共に「貞久の勢力…」の項で前述したとおりである。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「作手村誌57」〉で
注2)本文内で、縦書き漢数字で書かれている数値を横書きに改めて表記した箇所、年号に西暦を追記したところがあります。
注3)古石塔の所在記号が付されたものは、前項の分布図に表記されている箇所です。
《参考》
○ 古石塔とは、古くからある石造りの仏塔や石の塔を指します。
○ 石塔の種類?
層塔、宝塔、宝篋印塔、五輪塔、板碑、笠塔婆、無縫塔、石幢 など
○ 石塔の建立目的
仏塔は、仏教の開祖であるお釈迦様のお骨である舎利を納め供養する建物であるストゥーパ(サンスクリット語)に由来するといわれてます。
タグ :作手村誌57
2025年02月20日
6-06 中部地区の古石塔(5) (作手村誌57)
 『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。
『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。城址に続き、作手地区に残る古石塔についての記録です。
現在では、記事にある状況とは変わってしまっている場所もありますが、石塔が建てられた当時の“想い”や“願い”を感じながら、作手の歴史を辿っていきたいと思います。
********
第二編 歴史 - 第二章 中世
第十節 古石塔
(つづき)
*中部地区の古石塔
〔尾藤萬五郎墓〕 大字白鳥字新井(山林) (図33)
尾藤新三郎宅裏にあり、古来より尾藤屋敷といわれている。カヤの老樹の脇に石祠とともに宝篋印塔と一石五輪塔が1基ずつある。萬五郎は亀山城主奥平貞能の家臣で、貞能の命により弘治二年(1556)貞能の一族奥平伝九郎を本宮山の猿ヶ馬場で銃殺したと伝えられる小土豪である。その奥平伝九郎は川合(大字白烏)に居住していたといわれる。ところが「禅源寺旧記」では伝九郎が萬五郎を討ち取ると反対の記述となっていて、いずれが真実であるか明瞭でない。
○ 宝篋印塔(3基) いずれも砂岩製で破損がひどい。このうち2基は室町時代中期と末期、他の1基は江戸初期の造立である。室町中期と江戸初期のものは木造の小祠に尾藤家により祭られているが、全体の調和が不自然で、後世の他のものと混同されたことが明瞭である。
室町中期と推定のものの総高は54.4cmで、基礎15.5cm×17.2cm、塔身10.4cm×10.4cm、笠11.5cm×20.6cm、相輪17cm×8.5cmである。
また江戸初期のものの総高は、68.3cmで、基礎16cm賭けう21cm、塔身12.3cm×12.5cm、笠13.5cm×23.5cm、相輪26.5cm×8.6cmである。
この他に室町時代後期の一石五輪塔が1基と江戸時代初期の一石五輪塔が1基ある。
〔奥平家廟所〕 大字白鳥字北の入り(山林) (図29)
明治維新前までは、慶蔵寺という真言宗の寺があり、その境内の東端にあって、宝篋印塔6基と、一石五輪塔2基がある。現在は禅源寺に併合されているが、同寺の「旧記」によれば、亀山城主奥平貞俊・貞久・貞昌・貞勝・貞能の五代の改葬墓所で、慶蔵寺はこの墓守寺であったと云う。
○ 宝篋印塔(6基) そのうち室町中期末の笠の部分1個、江戸時代初期と考えられる部分5基分で、この内訳は基礎6、塔身2、笠6(残欠4)とまちまちの状態である。推察するに、奥平氏が作手を去ったのち、追悼の意味で建立したものの残骸であろう。その他ここには、江戸初期の一石五輪塔の欠損したものが2基ある。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「作手村誌57」〉で
注2)本文内で、縦書き漢数字で書かれている数値を横書きに改めて表記した箇所、年号に西暦を追記したところがあります。
注3)古石塔の所在記号が付されたものは、前項の分布図に表記されている箇所です。
《参考》
○ 古石塔とは、古くからある石造りの仏塔や石の塔を指します。
○ 石塔の種類?
層塔、宝塔、宝篋印塔、五輪塔、板碑、笠塔婆、無縫塔、石幢 など
○ 石塔の建立目的
仏塔は、仏教の開祖であるお釈迦様のお骨である舎利を納め供養する建物であるストゥーパ(サンスクリット語)に由来するといわれてます。
タグ :作手村誌57
2025年02月19日
6-05 中部地区の古石塔(4) (作手村誌57)
 『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。
『作手村誌』(1982・昭和57年発行)から「第二編 歴史 - 第二章 中世」-「第十節 古石塔」の紹介です。城址に続き、作手地区に残る古石塔についての記録です。
現在では、記事にある状況とは変わってしまっている場所もありますが、石塔が建てられた当時の“想い”や“願い”を感じながら、作手の歴史を辿っていきたいと思います。
********
第二編 歴史 - 第二章 中世
第十節 古石塔
(つづき)
*中部地区の古石塔
〔鳥居強右衛門勝商墓〕 大字鴨ヶ谷字門前(甘泉寺) (図16、18) 国指定天然記念物高野槇の根元にある。昔は高野槇の南側下に夫婦の墓が揃って在ったが、矢場を作るために強右衛門の墓だけ現在地に移転したといわれる。強右衛門は現在の豊川市市田の人で、妻は作手村大字清岳(市場)の紅谷家の出だと伝える。強右衛門は篠場野で磔死しその子庄右衛門信商は、1600(慶長5)年9月の関ヶ原合戦に臨んで信昌に仕えて出陣、石田三成の残党安国寺恵瓊を京都で生捕った。この功績により恵瓊の脇差正宗の名刀を給わった。次いで信昌の四男松平忠明に仕え、大坂夏の陣にも功をあげ1,000石を給付されている。ちなみに、この信商の子強右衛門正商は、忠明の二男八郎左衛門清道の家老となり、1,500石を給わっている。
 1602(慶長7)年松平忠明が、父祖の旧領作手藩1万7,000石の藩主として亀山城に入ると、庄右衛門信商も作手に移り、奥平氏の菩提寺である甘泉寺へ父勝商の墓を建立した。同寺には強右衛門の位牌があって、「智海常通居士 覚霊」とある。また裏面には「鳥居強右衛門尉三十六歳逝矣」と記され、台座裏面に「天正十五丁亥七月十六日塚守□也」との墨書がある。
1602(慶長7)年松平忠明が、父祖の旧領作手藩1万7,000石の藩主として亀山城に入ると、庄右衛門信商も作手に移り、奥平氏の菩提寺である甘泉寺へ父勝商の墓を建立した。同寺には強右衛門の位牌があって、「智海常通居士 覚霊」とある。また裏面には「鳥居強右衛門尉三十六歳逝矣」と記され、台座裏面に「天正十五丁亥七月十六日塚守□也」との墨書がある。○ 宝篋印塔(1基) 塔身は無く別物を使用してある。しかし、強右衛門のものにしては時代的にやや古く、型式からすると室町時代初期のものと推定される。したがって何時の時代かに取り違えたのではないかと思われ、今後の研究を要する宝篋印塔である。
総高は89.6cm、基礎25.5cm×27.5cm、塔身(別物)16.3cm×19.3cm、笠16.3cm×26cm、相輪31.5cm×10.5cmである。
〔甘泉寺開山堂裏の墓〕
甘泉寺は奥平家の菩提寺だといわれる。とするとここには、それ相応の古石塔が存在して良いはずであるが、今のところ、この墓以外に奥平氏関係とおぼしき古石塔は見当たらない。開山堂の一角に大形の相輪と、江戸初期と推定される宝篋印塔の破片があり、強いて言えば前者が奥平氏関係、後者が強右衛門のものではないかと判断される。ところが、前掲の「強右衛門」の墓と称する宝篋印塔は、時代的に見て、強右衛門の死以前に造立されたものと考えられるので、もし、これが強右衛門と無関係とされるならば、伝えられている「強右衛門の墓」は、あるいは奥平氏関係のものとも考えることができよう。
○ 宝篋印塔(6基) 総てバラバラであり、判断に苦慮する状態である。このうち室町中期及び江戸初期の基礎各1基、中形の相輪2基、大形の相輪最大径17cm 2基が存在する。この他に高野槇の南側下方、通称「強右衛門妻の墓」と伝えられる所に、相輪残欠1基、最大径13cm、笠残欠(別物)1基がある。これは室町中期と推定される型式で、伝承の「強右衛門の妻」の墓とするには、やはり年代が古い。たぶん別人のものと思われる。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「作手村誌57」〉で
注2)本文内で、縦書き漢数字で書かれている数値を横書きに改めて表記した箇所、年号に西暦を追記したところがあります。
注3)古石塔の所在記号が付されたものは、前項の分布図に表記されている箇所です。
《参考》
○ 古石塔とは、古くからある石造りの仏塔や石の塔を指します。
○ 石塔の種類?
層塔、宝塔、宝篋印塔、五輪塔、板碑、笠塔婆、無縫塔、石幢 など
○ 石塔の建立目的
仏塔は、仏教の開祖であるお釈迦様のお骨である舎利を納め供養する建物であるストゥーパ(サンスクリット語)に由来するといわれてます。
タグ :作手村誌57
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0cecb086.d8082110.0cecb087.43fbd927/?me_id=1213310&item_id=21375004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9059%2F9784198659059_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0cecb086.d8082110.0cecb087.43fbd927/?me_id=1213310&item_id=21340604&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2503%2F9784036492503_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0cecb086.d8082110.0cecb087.43fbd927/?me_id=1213310&item_id=21234252&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9071%2F9784104689071_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)