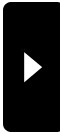2019年11月30日
上映『地球交響曲 第八番』
天気の良い日になりましたが,気温が上がらず寒い一日でした。
午後,あめんぼ読書会の主催する『地球交響曲 第八番』上映会を観に,つく交流館へ出かけました。
龍村仁監督の『地球交響曲』は,「第一番」が1992年11月に公開され,現在「第九番」の制作が進んでいます。
2015年に公開された「第八番」が一番新しい作品で,その上映でした。
「第一番」が公開された頃,学んでいた方が良さや価値を語って紹介されました。でも,その頃の世間(?)には“異端”だったように思います。
その後,「第二番」「第三番」と制作されていきますが,公開会場は限られており,広く知られる作品ではなかったようです。
自主上映が進むなか,徐々に“時代が変わって”きました。今,,「地球交響曲」の描く世界,その願いは“普通”になっているように感じます。

今日の会場に,多くの方が集まっていました。
「第八番」のナレーションで,先日亡くなられた 木内みどりさんが出演されており,その声が“ガイアの思い”に深まりを持たせているように感じました。
子育て世代,働き盛りの方々に鑑賞いただきたい作品でしたが,土曜日は“忙しい日”で,地元の子供の姿は見られませんでした。残念
感じること,考えること…が多く,心の疲れる作品でしたが,心地よい時間を過ごしました。
関係のみなさん,ありがとうございました。
【関連】
◇GAIA SYMPHONY ─ガイアシンフォニー─(オフィシャルWebサイト)
◇地球交響曲 @GAIASYMPHONY(Twitter)
◇地球交響曲 GAIASYMPHONY(Facebook)
◇新城市つくで交流館(Facebook)
【予告編など】
【開催中「つくで交流館まつり」】

午後,あめんぼ読書会の主催する『地球交響曲 第八番』上映会を観に,つく交流館へ出かけました。
龍村仁監督の『地球交響曲』は,「第一番」が1992年11月に公開され,現在「第九番」の制作が進んでいます。
2015年に公開された「第八番」が一番新しい作品で,その上映でした。

「第一番」が公開された頃,学んでいた方が良さや価値を語って紹介されました。でも,その頃の世間(?)には“異端”だったように思います。
その後,「第二番」「第三番」と制作されていきますが,公開会場は限られており,広く知られる作品ではなかったようです。
自主上映が進むなか,徐々に“時代が変わって”きました。今,,「地球交響曲」の描く世界,その願いは“普通”になっているように感じます。

今日の会場に,多くの方が集まっていました。
「第八番」のナレーションで,先日亡くなられた 木内みどりさんが出演されており,その声が“ガイアの思い”に深まりを持たせているように感じました。
子育て世代,働き盛りの方々に鑑賞いただきたい作品でしたが,土曜日は“忙しい日”で,地元の子供の姿は見られませんでした。残念
感じること,考えること…が多く,心の疲れる作品でしたが,心地よい時間を過ごしました。
関係のみなさん,ありがとうございました。
【関連】
◇GAIA SYMPHONY ─ガイアシンフォニー─(オフィシャルWebサイト)
◇地球交響曲 @GAIASYMPHONY(Twitter)
◇地球交響曲 GAIASYMPHONY(Facebook)
◇新城市つくで交流館(Facebook)
【予告編など】
【開催中「つくで交流館まつり」】

2019年11月29日
『謝罪力』(竹中巧・著)
 天気予報が,「今季一番の強い寒気が流れ込んで,朝は冷え込み…。」と伝えていた通りに,寒い朝になりました。
天気予報が,「今季一番の強い寒気が流れ込んで,朝は冷え込み…。」と伝えていた通りに,寒い朝になりました。霜が降り,氷点下の気温の朝でした。出かけるときの外気温3度,目的地まで気温の変化はわずかでした。
晴れて青空の綺麗な日で,日中は気温が上がり,帰路につくとき13度でした。寒暖差の大きさ,そし朝・夜の寒さに体が戸惑っているような感じです。
明日の朝も,寒そうです。暖かくして休みます。
ちょっと気になるタイトルをの『謝罪力』(日経BPマーケティング・刊)
マスコミが,幾度となく「申し訳ありません」と頭を下げるスーツ姿の謝罪会見を流しています。その様子から,すぐには何時の何のことだったのか分かりません。
“悪いこと”であれば,謝罪するのは当然ですが,今の世は「何時,当事者になるか分からない。」ような気がします。
「問題はいつの日か突然やってくる。」と,元吉本興業の広報担当で“謝罪マスター”の異名をもつ筆者が,具体的な事例から備えと対処を述べています。
今は「大謝罪時代」(第1章)であり,
テレビはその瞬間,新聞はその日,雑誌は次号が発売されれば話題は移るが,ネットの時代は移り変わりが早いと言うものの,アーカイブとしてずっとずっと先まで残るのである。正式でないものも間違いも,終わった問題であっても残り続けるのである。そして,それはいつになっても検索一発で,いつもで「今」に蒸し返される。「検索一発でいつでも,“今”,対策は“解決記録”」だと述べています。
謝罪に限らず,日々の営みが“過去の成功経験”から発想され,それに自信を得て行動しています。ところが,これまでの“経験”の多くは,ネットが存在していなかったり,影響も小さかったものばかりです。
残念ながら,“良い提案”も能率が悪かったり,さらに改善ができたりします。“失敗への対処”ではかえって悪化してしまうかもしれません。
そうした“今”を意識した対処や,さらには“あす(未来)”を考えた謝罪が必要なようです。
本書の紹介文に,
■謝罪は「目的」でも「ゴール」でもない。イカリ(怒り)をリカイ(理解)に変えようとあるように,事例を“自分ごと”としてハッピーエンディングに向かう対応と謝罪を考えてみませんか。
謝罪マスター・竹中功さんは言います。
――トラブルに直面した時,とりあえずマニュアル通りに深々と頭を下げておけば,何とかなる。やりすごせると思っていませんか。残念ながら,それは大きな間違いです。
謝罪は「目的」でも「ゴール」でもありません。直面する難題にも慌てず,謝罪の先に「ハッピーエンディング」を見定め,その実現のための「シナリオ」を描き,誠実に実行する。
そんな「謝罪力」は「より良く生きる力」に他なりません。「イカリ=怒り」を「リカイ=理解」に変え,より良い関係を築く。そんな力を鍛えていきましょう。本書には様々な「事例」を盛り込みました。
「その時,自分ならどうする?」。そんな気持ちで読み進めてください。
目次
はじめに
第1章 「大謝罪時代」を生きる
第2章 「謝罪力」とは
第3章 あの謝罪、何がいけなかったのか
第4章 こんな時、どうする?
第5章 家庭円満にも謝罪力が役立つ
第6章 「謝罪訓練」のススメ
【おまけ】 第6章の終わりに,「謝罪シナリオ」チェックリスト(p.251~)が載っています。シナリオを整えて「謝罪訓練」をしてはいかがですか。
■シナリオ準備編詳しくは本書で。
・謝罪を成功に導く6つのステップ
■シナリオ作成編
0:状況設定
1:挨拶・自己紹介
2:謝罪
3:経緯・原因
6W1Hで確認
4:再発防止策
6W1Hで確認
5:賠償
6:質疑応答
7:最後に再度謝る
8:締めの挨拶
■アクション編
・アポイントを取り,訪問日を決める
・謝罪当日
・注意すべきNGポイント
・後日
【おまけ】
◇「Emication」の読書はこちら
2019年11月28日
寒い日。企画展「防災を考える」。
 予報通りに曇った空そして時々雨の降る真冬のように“寒~い”一日でした。
予報通りに曇った空そして時々雨の降る真冬のように“寒~い”一日でした。今日からつくで交流館で,企画展「防災を考える ~東日本大震災の教訓~」の写真展示が始まりました。
地震や台風,豪雨による自然災害が後を絶ちません。そればかりか,今後,さらに広域化・甚大化する恐れがあると言われています。「南海トラフ地震」がいつ起きてもおかしくない状況と叫ばれています。いざという時の身近な備えや心構えはできていますか。今日は,写真を撮影した写真家・防災士の
東日本大震災から8年半,大震災の状況やその後の被災地の現状を知り,災害や身近な防災について考え,備える機会にしたい(略)
三浦寛行氏の講話「はるかのひまわりがつなぐ 震災の記憶 そして希望」があり聴講に行きました。
「はるかのひまわり」は,阪神淡路大震災の被災地に咲いたものです。東日本大震災の後,東北で花を咲かせ,それが新城市に届き,毎年綺麗な花を咲かせます。
その縁を結んだのが新城市出身の三浦氏です。大震災から6か月後(2011/09/01),千郷中学校の生徒が横断幕を託しました。
ここから,交流が始まりました。

平成23年4月
3.11の津波で瓦礫だらけの釜石へ、絵本作家の指田さんが、神戸の復興の花「奇跡のひまわりの種」を持ってきました。
その夏、釜石市(奇跡の釜石)と陸前高田(奇跡の一本松)で咲き、見る人みんなを元気にしました。
平成23年9月
千郷中学校は釜石東中のみんなを元気にさせたい想いで「ひまわりの横断幕」を夏休み中に制作し、2学期の始業式に私が釜石東中学校へ持って行きました。
「ひまわりの横断幕」は今でも釜石東中学校の仮設校舎の玄関に飾ってもらっています。友情の証です!
平成24年夏
「奇跡のひまわりの種」は奇跡の集落と呼ばれている大船渡市立吉浜中学校の花壇にも咲きました。
平成25年春
「あの日を忘れない 奇跡のひまわりの種」は奇跡の里を巡って、新城市立千郷中学校に届きました。千郷中学校では花壇に植え、今では写真の様にすくすくと育っています。みんなでひまわりが咲くのを楽しみにしています。
こうやって東北の子供たちと交流を続ける。東日本大震災のこと阪神淡路大震災のことをみんなで考える、忘れない。中学生としてできる被災地支援をする。良いことです。
来年は「奇跡のひまわりの種」が新城、三河、愛知ともっともっと拡散したら素敵ですね!(三浦氏のfacebookより)
講話では,東日本大震災の2011年から2019年の今までの様子,三浦氏が出向いた熊本地震,大雨や台風の被災地の状況など,記録した写真や資料を使って語っていただきました。
会場には,l小学生や中学生が多く,子供達に分かりやすい内容と語り方でした。
作手小学校に「はるかのひまわり(奇跡のひまわり)」が花を咲かせたのは,2014年の夏でした。
今年のラグビーワールドカップでは,新城市で咲いた「はるかのひまわり」が,釜石市の会場を飾りました。それに添えられたカードを作手小学校の子供達が書いています。
ラグビーワールドカップを飾ったひまわり,皇居に咲いたひまわり…,それらが自分達と“深い縁”のあることを聞き,それぞれの大輪を思い浮かべているようでした。

三浦氏は,「この夏にも“作手地区ではるかのひまわりを咲かせ”て欲しい」と会場のみなさんに伝え,講話を終えました。
子供達,地域の方々が,地域の防災を考える講話でした。
企画展をきっかけに,“新しい一歩”が始まりそうです。
三浦さん,ありがとうございました。
【ひまわりの話題;学校ホームページより】
◇作手小学校の「ひまわり」
◇千郷中学校の「ひまわり」
【関連】
◇情熱のソーシャルカメラマン(Facebook)
◇三浦 寛行(Instagram)
◇奇跡のひまわりプロジェクトin新城(Facebook)
◇新城市つくで交流館
◇新城市立作手小学校
◇新城市立作手中学校
【おまけ】
2019年11月27日
思い。『365日の親孝行』(志賀内泰弘・著)
 曇り空,そして小雨の降る,湿った日でした。
曇り空,そして小雨の降る,湿った日でした。“年の瀬”が近づいてくると社会福祉協議会やボランティア団体の“歳末たすけあい”の呼びかけが聞かれるようになります。
秋(冬?)には赤い羽根共同募金もあったと思いますが,勤めを終えると,それを知らずに過ぎています。
そうした中,防寒支援や命の支援を続ける手紙が届きます。
絵はがきとペン,そこに“思い”を感じます。いつものように住所と名前を記しました。
新しい年まで1か月。
少し前に,『京都祇園もも吉庵のあまから帖』を読ませていただいた志賀内泰弘氏から『365日の親孝行』(リベラル社・刊)
題名を見て「どこかで聞いたような」と思いませんか。著者は
「親孝行」プロジェクトの一つが、本という形になって出版になります。タイトルは、「365日の親孝行」(リベラル社)です。と述べています。
え?! アイドルグループのヒット曲に似てるって?
はい、似てます(笑)
まえがきを,
この本を手に取って下さった「あなた」は、おいくつでしょうか?と問いかけで始めています。
もし、40歳で、もう、故郷から遠く離れて都会で暮らしているとしたら、お父さん、お母さんが天国に行かれるまで、あと何回会えると思いますか?
さて,あなたは何回ですか?
もくじを見ると,「1月 ふるさとに帰省するのは一年ぶり。…」のように,12月まで順に書かれており,365日に「親孝行のススメ」が述べられているのか思いました。
1ページめくると「親孝行アイデアリスト」があり,
○何をしたらいいかわからないにある項は,4ページの記述(ショートストーリー)ですが,他は短いアイデアコメントです。
○ 忙しくて時間がとれない
○ お金にあまり余裕がない
○ 同居または近くに住んでいる
○ 離れて暮らしている
○ 親と一緒に何かをする
○ ものでなく心を贈りたい
○ たまには贅沢させてあげたい
○ 孫との時間を贈りたい
○ 親との距離を縮めたい
○ 親ができないことを代わりにやってあげたい
○ 親の身体が不自由になったら(介護中など)
また,329~364は“親孝行グッズ&サービス”の紹介です。
読み進めながら“親孝行”が思い浮かべると思います。これまで,「それでは…。」と動き出すには,もう一つ至らなかった方も,本書のアイデアには,「これならできる。」というものが見つかることでしょう。
本書は,働き盛りの世代,子育て世代の方々にお薦めです。
どこから読む事もでき,流し読みしてから,気になったところに戻って,しっかり読み,行動を考えてはいかがでしょう。
さて,お父さん,お母さんに,あと何回会えますか?
もくじ
まえがき
親孝行アイデアリスト
親孝行自己診断チェックシート
お父さん、お母さんにありがとうメッセージ
親孝行グッズ・サービス紹介
あとがき
※本書は「いい話の図書館」で届いた図書ではありませんが,“縁”をもって下記も掲載します。
【「いい話の図書館」 これまでに紹介した本】
◇『よっぽどの縁ですね』(大谷徹奘・著)(2019/11/ )
◇『「あの商店街の、本屋の、小さな奥さんのお話。」』(高橋しん・著)(2019/11/06)
◇『京都祇園もも吉庵のあまから帖』(志賀内泰弘・著)(2019/10/23)※10月に同封
◇『雪とパイナップル』(鎌田實・著)(2019/10/06)
◇『負けるな、届け!』(こかじさら・著)(2019/08/31)
◇『気象予報士のテラさんと、ぶち猫のテル』(志賀内泰弘・著)(2019/08/18)
◇『本のエンドロール』(安藤祐介・著)(2019/08/10)
◇『Life(ライフ)』(くすのきしげのり・作/松本春野・絵)(2019/06/30)
◇『勇者たちへの伝言』(増山実・著)(2019/05/29)
◇『スタートライン』(喜多川泰・著)(2019/05/22)
◇『眠る前5分で読める 心がスーッと軽くなるいい話』(志賀内泰弘・著)(2019/04/10)
「いい話の図書館」とは…本との出逢いは,人生を変えます。辛い時,悲しい時,一冊の本が「生きる希望」を授けてくれます。
そこで,ステキな本との出会いを提供する「いい話の図書館」を全国津々浦々に作ったら,どんなに素晴らしいだろうと考えて館主を募集しております。「いい話の図書館」の館主のお仕事は,本棚にステキな本を並べて多くの人に自由に読んでいただくこと。そのステキな本は,テレビをはじめ,マスコミでも話題の小林書店のカリスマ店主,小林由美子さんが心を込めて推薦する本です。
◇いい話の図書館【申込】
◇小林書店さん (@cobasho.ai)(Instagram写真と動画)
◇志賀内 泰弘(Facebook)
◇プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動(note)
【おまけ】
◇「Emication」の読書はこちら
2019年11月26日
「城の縄張と軍事概観」(続 つくで百話)
 「曇り空から雨になり,気温が下がって…。」と思っていましたが,傘をさすことなく活動ができました。また,寒くはなく,むしろ暖かい日でした。
「曇り空から雨になり,気温が下がって…。」と思っていましたが,傘をさすことなく活動ができました。また,寒くはなく,むしろ暖かい日でした。今年の冬も暖冬かな…。明日の天候は…。
『続 つくで百話』(1972・昭和47年11月 発行)の「作手のお城物語」からです。
公益財団法人日本城郭協会が「日本100名城」「続 日本100名城」を選定し,公表してから,当地の城址・古城を訪ねる方が増えています。その方々にも伝えたい記事です。
********
作手のお城物語(設楽町 沢田久夫)
城の縄張と軍事概観
城郭を構えるにはまず「縄張」が大切です。縄張は経始とも書き,全体的な土地利用計画のことで,縄を張ってここは濠,ここは土塁,ここは本丸,ここは塀,門,とそれぞれ土地の配分計画に基き実施されます。城郭研究の権威大類伸博土は,郭の構成計画を分類して輪郭式,同変形,梯郭式,同変形,連郭式の五つとしましたが,連郭式が前者の組合せによって作られたものとすると,基本は輪郭式と梯郭式ということになります。
輪郭式というのは,大中小と大きさの違った鉢を積重ねた形に似ているところから,江戸時代は,これを入子鉢形といいました。また鉢の縁を一方にそろえて積み重ねると,その形が橋の欄干の擬宝珠を斜上から見た形になるので,これを輪郭式変形とし,階段状に郭が積上げられるのを梯郭式としました。しかし実際に城を踏査してみると,郭の組み合わせと形状は千差万別で,どの類型に属するか判定に苦しむ場合が少くありません。そこで私は以上の分類を参考にして,奥三河並びに隣接地方の城郭の型を,次の六つにしました。
円心円階段 入子鉢形
偏心円階段 擬宝珠形
直線双階段 本丸を中心に両側へ階段状をなすもの
直線片階段 片側のみ階段状
単 郭 郭が一つだけ
連 郭 二つ以上の郭が接続せずやや離れて存在する
比較的規則正しい標準的な型では,中央高所に本丸があり,二の丸三の丸と同心円的に配置されており,この外に派生的に付属している郭をその方角によって西の丸北の丸などと呼びます。詰の丸というのは一城中最も奥にある最後の拠点となる郭です。城郭の外部にあるものを内郭に対し外曲輪,総曲輪といい,ここには下級武士の住居や城下の一部が入っています。
 鎌倉時代の作手地方は,土豪武士の揺らん期でしたから,一団の人数は少なく,多くとも数十人を出なかったと考えられ,それらは本家を中心とした一族郎党の集りでした。それは後のように,顔も知らない多数の人間を方々から集めた軍団のように,隊伍的組織と規則を以て束縛したのとは違い,家族的で主従生死を共にするという情誼を以て結ばれた一団でした。そうした彼等の目的は,自己領域内の安寧秩序を保ち,他から侵害されぬよう自衛するためでした。
鎌倉時代の作手地方は,土豪武士の揺らん期でしたから,一団の人数は少なく,多くとも数十人を出なかったと考えられ,それらは本家を中心とした一族郎党の集りでした。それは後のように,顔も知らない多数の人間を方々から集めた軍団のように,隊伍的組織と規則を以て束縛したのとは違い,家族的で主従生死を共にするという情誼を以て結ばれた一団でした。そうした彼等の目的は,自己領域内の安寧秩序を保ち,他から侵害されぬよう自衛するためでした。こうした自己本位の小集団をいくつか集め,一門の惣領とか,有力な豪族がその全体を指揮したのが当時の軍隊でした。従って全軍の連絡は当然悪く,甚しきは主将の命令すら徹底せず,利害相反したり,或は何か気に入らぬことがあると,自己の部下を率いて戦場から離脱し,帰国してしまうことすらありました。新田義貞が千早城攻囲戦の途中で,病と称し部下をまとめて上野国へ帰ったのもその一例です。これも当時の一般社会に統一力が乏しく,自己本位だった時代相の反映でしょう。
室町時代の中頃までの武士は,ただ武芸専業の武者ではなく,平時は農耕にはげみ,一旦事ある時には城に詰めたり,或は戦場に馳せたりしました。一領具足という言葉がありますが,これは何がしの領地をもち,一通りの武具をもった者という意味で,こうした武士たちが,奥平氏菅沼氏などを統領とし,「山家三方衆」という武士団を形成したのです。彼等は田畑で耕作している時も,畦道には刀槍や鎧櫃を用意していました。即ち敵襲が迫ると,まず城中で鐘がつかれ,つぎに太鼓が鳴らされ,ついで法螺貝が吹かれることになっていました。それを聞くと彼等は直ちに鋤鍬を捨て,その足で武具を携えて入城し,点検を受けました。
一番に鳴る局は鐘で,それを合図に彼等は城中に兵糧を運び入れます。二番目に鳴るのは太鼓で,それを合図に甲冑に身を固めます。三番目に鳴るのが法螺貝で,武士も百姓も残らず城中に龍りました。これは千葉市の近郊土気城のやり方ですが,地域により多少の相違はあるとしても,大筋は全国共通のものでした。もちろん,これらの武士は,平時でも年に何日かは本城に出向いて,大番を勤めました。
もちろん戦国の頃になると,旗本と呼ばれる専門の武士が居なかったわけではありません。しかしその数は僅少で,とても兼業武士とは比べものになりません。戦闘カ──訓練や能力では,はるかに専業武士の方が優秀ですが,領主の勢力が小さく,武土団の人数が少いところでは,たとい戦力に影響があっても,城下の1ヶ所にまとめることは不可能でした。一方の旗頭であった田峯菅沼氏にしても,その苗字の地は,現在の大字程度のものに過ぎず,その領地も二十数ヶ村にすぎない小勢力でした。
次に兵器戦法についてみると,戦闘はまず約一町を隔てて矢戦から始まります。矢戦が一わたりすむと個人の騎馬戦となり,まず大刀を揮って戦い,更に近づいて組打ちとなる。相手を組伏せ,小刀を以て急所をさし敵を斃すという順序です。歩卒は薙刀を以て馬上の敵に当り,時に馬の脚を薙払ったり,熊手を鎧にひっかけてずり落しました。弓は一町ぐらい先まで届きましたが,実際に致命的な効力を発揮する距離はぐっと短く,せいぜい十五間と,兵学者はその矢がかりを踏んでいます。長柄の槍が現れてくるのは,南北朝の終わり頃からです。歩騎の比率も半々くらいであったのが,後になるほど歩兵の比率がぐんと増加し,従来の騎馬武者による個人戦法から、歩兵を中心とする団体戦法へと転換していきます。
********
注)これまでの記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
【関連】
◇公益財団法人日本城郭協会
タグ :続つくで百話
2019年11月25日
『よっぽどの縁ですね』(大谷徹奘・著)
 “暖かい日”でした。当地でも20度近くまで気温が上がりました。
“暖かい日”でした。当地でも20度近くまで気温が上がりました。季節外れの天候に,居心地の悪さを感じました。
ここ数日で,木々の紅葉が進んだようです。色が鮮やかになり,美しさが増したようです。
“今”を楽しみました。
新しい学びをしたいと準備をしていたことが整い,新しい週の始まりに合わせて,資料を開きました。
資料の量,期間から「1日8ページの学習」を予定にしました。これで一通りの学びです。復習や繰り返しを考えると,少しペースを上げた予定にした方がよさそうです。
新しいことを学ぶことは嬉しいことです。
楽しい時間が過ごせそうです。
「いい話の図書館」で届いた10冊目の図書です。
今回の本は,講演会(法話)を書籍化した『よっぽどの縁ですね: 迷いが晴れる心の授業』(小学館・刊)
小林店長からのメッセージは,
手を合わせる──それは宗教心とかではなく,二心(ふたごころ)のない証だといいます。でした。
後ろ手をすると,見えない手で刃物を持っていると思われる。
懐に手を入れていると,中で危険物を持っていると思われるかもしれない。
あなたに悪意を持っていないことを,前で手を合わせることで表したのだと,この本で知りました。
この世に偶然はない,すべて「縁」で繋がっている。
というお話も素直に読める一冊です。
副題の「迷いがはれる心の授業」,帯の「あなたは大谷徹奘の「心の授業」を聞いたことがありますか?」から,CDで大谷氏から語っていただこうかと思いましたが,先に読みました。
大谷氏の法話を聞いたことはありませんが,優しい穏やかな声,そして力強い声で語りかけられているようでした。
氏は「命を使って勉強する時間を与えられた」と言い,そのなかで「言葉」がプレゼントされました。

最初は,幸せを考える大きなヒントとなる,お経に出てくる四文字『身心安楽』(しんじんあんらく)でした。
その意味は…。(本書で)
さらに「縁」,そして『よっぽどの縁』へ。
迷いから悟へ,『自覚悟』を。
それは…。(本書で)
「よっぽどの縁」に幸せを感じ,明日への元気を感じる,大谷氏の法話です。
語られる言葉に,あなたは,何を見出しますか。
目次
この国が平和だからこその出会いがある
「幸せ」の定義を教えてくれる四文字の言葉
人間関係の「縁」を受け止める六文字の言葉
迷いの中から悟りを得る三文字の言葉
あとがきにかえて「よっぽどの縁」誕生物語
【「いい話の図書館」 これまでに紹介した本】
◇『「あの商店街の、本屋の、小さな奥さんのお話。」』(高橋しん・著)(2019/11/06)
◇『京都祇園もも吉庵のあまから帖』(志賀内泰弘・著)(2019/10/23)※10月に同封
◇『雪とパイナップル』(鎌田實・著)(2019/10/06)
◇『負けるな、届け!』(こかじさら・著)(2019/08/31)
◇『気象予報士のテラさんと、ぶち猫のテル』(志賀内泰弘・著)(2019/08/18)
◇『本のエンドロール』(安藤祐介・著)(2019/08/10)
◇『Life(ライフ)』(くすのきしげのり・作/松本春野・絵)(2019/06/30)
◇『勇者たちへの伝言』(増山実・著)(2019/05/29)
◇『スタートライン』(喜多川泰・著)(2019/05/22)
◇『眠る前5分で読める 心がスーッと軽くなるいい話』(志賀内泰弘・著)(2019/04/10)
「いい話の図書館」とは…本との出逢いは,人生を変えます。辛い時,悲しい時,一冊の本が「生きる希望」を授けてくれます。
そこで,ステキな本との出会いを提供する「いい話の図書館」を全国津々浦々に作ったら,どんなに素晴らしいだろうと考えて館主を募集しております。「いい話の図書館」の館主のお仕事は,本棚にステキな本を並べて多くの人に自由に読んでいただくこと。そのステキな本は,テレビをはじめ,マスコミでも話題の小林書店のカリスマ店主,小林由美子さんが心を込めて推薦する本です。
◇いい話の図書館【申込】
◇小林書店さん (@cobasho.ai)(Instagram写真と動画)
◇志賀内 泰弘(Facebook)
【おまけ】
◇「Emication」の読書はこちら
2019年11月24日
ローマ教皇来日。「誉め言葉」
 朝は「晴れるかな?」と思える空でしたが,日差しのあるなかで小雨だったりする不順な天候の日でした。
朝は「晴れるかな?」と思える空でしたが,日差しのあるなかで小雨だったりする不順な天候の日でした。気温は低くなく,暖かい一日でした。
ローマ・カトリック教会の教皇として,38年ぶりに日本を訪れているフランシスコ教皇が,ナガサキ,ヒロシマを訪れています。
ローマ教皇は,今回の訪問で,原爆が落とされたあとの長崎で「焼き場に立つ少年」の写真を撮影した,アメリカ軍の従軍カメラマン ジョー・オダネル氏の息子と面会をしたそうです。この夏の記事で,教皇と写真の話題を取り上げました。

キリスト教徒ではありませんが,核廃絶を願う教皇が,今回の訪問でどのようなスピーチ,発信をするのか関心をもっています。
教皇の声に,あなたの思いは…。
話は変わりますが,言葉の話題です。
“褒めたい”と思いながらも,なかなか言葉になってきません。
出会った相手に,こうした言葉が言えたら,新しいコミュニケーションが生まれるような気がします。
○「今日も素敵ですね。」いかがですか。
○「笑顔が素敵ですね。」
○「目がすごくキレイですね。」
○「いい仕事しますね。」「(仕事が)デキるなぁ~(笑)」
○「いつも一生懸命ですね。」
○「頼りになりますね。」
○「努力しているのですね。俺もがんばらないと。」
○「人間として、憧れます。あなたのような人間になりたいです。」
○「一緒にいて落ち着きますね。」「一緒にいると楽しいです。」
○「(〇〇さんがいると)周りのみなさんが笑顔になりますね。」
○「(あなたに)会えて良かったです。」
【関連】
◇Pope Francis (@Pontifex)(Twitter)
◇教皇フランシスコ(邦訳) (@chuokyo_pope)(Twitter)
◇終戦記念日。「わんかせぶち」(つくで百話)(2019/08/15 集団「Emication」)
◇『焼き場に立つ少年』。(2017/08/10 集団「Emication」)
◇ローマ教皇 長崎 広島でのスピーチ(全文)(NHK)
タグ :言葉
2019年11月23日
勤労感謝の日。学習発表会。学校運営協議会。
最近の寒さ,昨日の雨とは異なる“暖かい日”になりました。
今日は,祝日の一つ「勤労感謝の日」でした。「勤労をたっとび,生産を祝い,国民互いに感謝しあう」ことを趣旨とした祝日です。自然の恵み,日々の営みに感謝する日でした。
今日は,作手小学校の学習発表会があり参加しました。
つくで交流館ホールでの開催も,回を重ねて,火曜日(19日)の公開(地域の方々向け)を含め“かたち”が整ってきたよように感じました。
子供達の発表・演技は,聞き取りやすい大きな声でした。
そして,学習の活かされた内容,工夫のある演出で,会場のみなさんを引き込んでいました。

それぞれの学年に合わせた成長を感じる,心地よい時間でした。
ありがとうございました。
午後,第3回作手地区学校運営協議会が行われました。
さまざまな意見,質問が出されたり,課題・懸案事項の検討や対応を話し合ったりして,「より良い教育環境づくり」を考えました。
これからの子供達の成長,地域活動の広がりが楽しみになる時間でした。
委員のみなさん,ありがとございました。
午後,地区の神社で,秋の収穫に感謝する「新嘗祭」が執り行われましたが,学校運営協議会と重なり,参拝できませんでした。
新嘗祭は,天皇が五穀の新穀を天神地祇に勧め,また,自らもこれを食して,その年の収穫を感謝する祭儀に由来します。
帰宅後,神社に向かって,今年の恵みに感謝しました。拝
【関連】
◇作手こども園
◇新城市立作手小学校
◇新城市立作手中学校
◇愛知県立新城東高等学校作手校舎
◇新城市つくで交流館
今日は,祝日の一つ「勤労感謝の日」でした。「勤労をたっとび,生産を祝い,国民互いに感謝しあう」ことを趣旨とした祝日です。自然の恵み,日々の営みに感謝する日でした。
今日は,作手小学校の学習発表会があり参加しました。
つくで交流館ホールでの開催も,回を重ねて,火曜日(19日)の公開(地域の方々向け)を含め“かたち”が整ってきたよように感じました。
子供達の発表・演技は,聞き取りやすい大きな声でした。
そして,学習の活かされた内容,工夫のある演出で,会場のみなさんを引き込んでいました。

○児童代表あいさつ,全校合唱「スマイル・アゲイン」
○劇;3年「こびとのくつや」
○劇;1年「サラダでげんき」
○劇;5年「生きている入場券」
○PTA会長あいさつ
○劇;2年「11ぴきのねこ」
○劇;4年「先生、しゅくだいわすれました」
○劇;6年「あの日の空は~豊川海軍工廠~」
○児童代表 お礼のことば

それぞれの学年に合わせた成長を感じる,心地よい時間でした。
ありがとうございました。
午後,第3回作手地区学校運営協議会が行われました。
○会長あいさつ最初に,学校から最近の教育活動について説明があり,それを受けて意見交換をしました。
○議題
・作手こども園から報告
・作手小学校から報告
・作手中学校から報告
○意見交換
○閉会行事
さまざまな意見,質問が出されたり,課題・懸案事項の検討や対応を話し合ったりして,「より良い教育環境づくり」を考えました。
これからの子供達の成長,地域活動の広がりが楽しみになる時間でした。
委員のみなさん,ありがとございました。
午後,地区の神社で,秋の収穫に感謝する「新嘗祭」が執り行われましたが,学校運営協議会と重なり,参拝できませんでした。
新嘗祭は,天皇が五穀の新穀を天神地祇に勧め,また,自らもこれを食して,その年の収穫を感謝する祭儀に由来します。
帰宅後,神社に向かって,今年の恵みに感謝しました。拝
【関連】
◇作手こども園
◇新城市立作手小学校
◇新城市立作手中学校
◇愛知県立新城東高等学校作手校舎
◇新城市つくで交流館
2019年11月22日
小雪。「お城を構成する要素」(続 つくで百話)
 今日は,二十四節気の一つ「小雪」です。以前は,この日に合わせるように雪が降ったことがありますが,今日は雨の一日でした。
今日は,二十四節気の一つ「小雪」です。以前は,この日に合わせるように雪が降ったことがありますが,今日は雨の一日でした。寒くなったとはいえ,今年の雪は,もう少し先のようです。
今年の冬は,どんな天候になるでしょうか。
『続 つくで百話』(1972・昭和47年11月 発行)の「作手のお城物語」からです。
********
作手のお城物語(設楽町 沢田久夫)
お城を構成する要素
太古極めて少数の人が,広漠たる大自然の中に住んだ頃は,まず森に棲む野獣の襲撃から身を守ることが第一であり,ついで人口が増加すると,集団同志の間に競争が起り,対立が生れます。対立は時として闘争に及び,血を流すこともあったでしょう。そこで社会の安寧を保ち,集団,氏族,国家の存在を全うするためには,自らを守る軍備が必要となります。
まず,天然の地形を利用して,その能率を高めることを考えますが,更に進んで,そこに人工的な防禦施設をした方が,一層よいということを知るようになり,ここに始めて築城ということが始まりました。城または城郭ともいい,一言にしていえば,軍事目的をもって構築した防禦施設ということになります。従って城の形や種類も,時代により,所により,目的によって千差万態です。
城郭を構成する要素を,その工事の上から大別しますと,土工と建築とに分けられます。前者は天然の地形を利用して塁濠などを構築するもので,城郭構成上最も重要であり,且つ基本的なものです。後者はその上に建築されるもので,前者に比べると従属的な位置におかれます。江戸時代の軍学者は前者を普請,後者を作事といいました。
土工の主たるものは塁と濠です。これは城郭構成の基本で,塁は「土居」といい,土を以て築き上げるのが普通でしたが,近世になると石垣を以てその表面を固めるようになりました。また石垣と土居を併用し,上部もしくは下部,外側のみを石垣とする場合もあります。しかし石垣を築くということは,大へんな労力と財力を必要とします。従って山家三方衆程度の実力では出来なかったと見え,作手の城に石垣は見られません。
城塁には曲折の有るものと無いものとあり,曲折に直線状のものと曲線状のものとあります。主として自然の地形に従う山城では,概して曲線的ですが,人工を主とする平城では直線的なものが普通です。城塁の高さ及び幅は,城の規模の大小と地形によって一様ではありませんが,近世の軍学者は,まず高さは城内の平面から三間,幅は項で二間,基底が八間を以て標準としました。
これらの塁には城兵が拠って戦うために必要な通路や階段がついており,その位置,形状,大小も軍学者の研究の一部で,塁の外部には濠のあるのが普通です。濠には水のあるものと無いものとあり,両者の中間に位するようなものもありました。水のないのを「空堀」といい,山城に主として用いられ,平地でも水利の悪い所では之を用いました。両者の中間に位するのが「泥田堀」で,これは低湿地に用いられ,舟を浮べることもできず,さりとて徒渉も不可能という,防禦には却って都合がよいものでした。
堀と関聯して注意すべきものに,井戸,池,上水道,下水道,塵捨場などがあります。生きとし生けるもの水がなくては一日も生きてゆけません。そこで飲料水の確保に最善の努力が払われました。「築城記」という兵書に「山城では十分に水を試してから構えるべきで,谷のある山の尾根を堀切り,水の近くの木を伐って,水の溜るようにしておくべきである」と説いています。そこで用水の便の悪い山城では,池を堀り水の漏らないように池の内部を赤土で叩き固め,壁のように塗り廻し,軒の雨水を一滴も余さず懸樋で導いて池に溜めました。又大甕をいくつか備え,天水をこれに貯えるということは,最も普遍的な飲料水対策でした。
建築物及びこれに準ずるものの構造は,時代と場所によってかなりの相違がありました。その最も簡単なのが,自然の樹枝樹幹を利用した鹿砦(逆茂木)です。普通には臨時にこれを構えますが,平常からこれと同じ目的で植樹しておく場合もあります。軍学者はこれを「植物」といい,茨や棘の多い枳穀,寨勝などはその目的にぴったり,丈の高い植物は隠蔽の用も兼ねました。戦時には通路や濠中に菱を撒いて敵の通行を防げました。ヒシは小さい鉄製の四つの棘をもったものでどんな風に転しても一つは必ず上向きで,履物の悪かったむかしは随分と威力を発揮しました。
柵に板を張ったのが「板塀」で,これに耐火耐久の目的で表面を土で塗ったのが「塗塀」です。木を用いず全然土と瓦で築い「築地」や塗塀の表に瓦を張った「海鼠塀」がありますが,これらは余程の大城でないと見られません。塀は塁上又は崖上にこれを建連ねて敵の侵入を防ぐと共に,城内を隠蔽し且つ矢石弾丸を防ぐのが目的です。しかし塀は動かないので,戦時には臨時に楯を利用しました。杭も簡単ですが,騎馬の突進を妨げるには有効でした。
木戸は城戸で臨時築城によく用いられました。山城では険路を扼し,柵につづき地形によっては二重三重にしました。材料は付近有合せの木材で堅固を旨とし,これに格子になった扉をつけました。こうすれば近づく敵に矢を射かけ,或は刀槍を以て打払うに便利でした。
城の出入口には門を設け,濠には橋が架けられました。門も両側に柱を建てただけの簡単なもの,之に木を渡した株木門から,屋根のあるもの,上に桟敷のあるもの,楼門としたものなど種々ですが,何れも扉をつけ開閉できるのが普通です。また塁を断ちきらず「埋門」としたトンネル式のものもありました。門の材料は木材ですが,後には金属板を張ったものが出ました。門の内部に矢らいや柵を設けて更にここに門を設け,塁を以て築いたのがいわゆる桝形式城門で「虎口」「馬出し」ともいいました。
城塁上に建てられ平常は住居とし,或は兵器糧食を貯え,戦時にはこれに拠って戦う建物があります。これを「長屋」とも「多門」ともいいます。また展望や俯射に便するために,これを二重三重にしたものを「櫓」といい,その位置,目的,形式によって隅櫓,月見櫓,二重櫓など様々に呼ばれました。これらの櫓から発達して,城の中央に最も大きく建てられたのが「天守」ですが,これは戦国時代でも一番終りでないと出てきません。これらの塀,多門,櫓には,外部を眺めたり矢弾丸を発射するための窓が明いています。これが「狭間」で,矢狭間,鉄砲狭間等といい,その形状,位置は軍学者の研究領域でした。なおまた城門,塀,石垣等には敵兵が近寄った際打ちかけるべき「石落し」の仕掛のあるものもありました。
尚この外に,城内には兵器糧食の貯蔵庫,城主や重臣の邸宅,厩舎,平時の政庁などの諸建物があったことは云うまでもありません。城郭は以上の構成要素を,その目的により城郭の大小に応じて,選択組合せて築城したわけで,時代を遡るほど簡単素朴でした。作手地方最大最強の規模をもつ亀山城にしてからが,石垣はなく虎口の存在も不詳で,普請も実用一点張り,塀の如きもざっとした塗塀の域を出なかったのではないかと思われます。
********
注)これまでの記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
2019年11月21日
『AI時代を切りひらく算数』(芳沢光雄・著)
 今朝,冷え込みました。
今朝,冷え込みました。確認した時,「気温1度」でした。明け方は氷点下だったかもしれません。
“寒~い”朝でしたが,その後は日差しのおかげで“暖か~い”日中でした。寒暖差の大きさに,体がついていけない気がします。
市内の学校で,インフルエンザに罹患した児童・生徒が出ているようです。体調管理をしっかりと。
春に,著者の“提言”に「なるほど」と感じた『「%」が分からない大学生』(2019/06/18)を読みました。
その記憶から,書名にある「AI時代」に興味をもって『AI時代を切りひらく算数 「理解」と「応用」を大切にする6年間の学び』(日本評論社・刊)
帯や扉で,
「分数ができない大学生」や「%が分からない大学生」は,小学校算数の「やり方」の暗記に原因がある!と,算数・数学の苦手な人が“学び直し”のできる本だと楽しみに本を開きました。
長年いわたり算数・数学教育に携わってきた著者が,中学や高校数学の立て直しだけでは手遅れと感じ,「理解」と「応用」を大切にした小学校6年間の算数の新しい学びを示します。
佐藤優氏(作家・元外務省主任分析官)絶賛!
「算数と数学の勉強の仕方がよくわかる。芳沢光雄先生にしか書けない、数学嫌いの真理をよく踏まえた本」
「あれっ。ちょっと違うぞ。」
ハードルが高そうです。まえがきのなかで,
日本の数学教育全般を眺めて見ると,小学校の算数教育が重要であるにも関わらず,それを軽んじている社会全体の意識を残念に思うことかあります。算数教育の現場に目を向けると,理解に苦しむ指導法がいろいろ目につきます。マークシート式問題が全盛で記述式問題が軽視される時代を反映して,数学は答えや性質を導く教科であるにも関わらず,「やり方」を覚えて答えを当てる教科だと勘違いされている面もあります。また「ゆとり教育」時代の算数教科書には, 18ページの表で示すように本質的な問題点もありました。と,「算数指導書の提案」であることを述べていました。
本書は,上で述べてきたことの反省の視点に立って, AI時代の算数指導書の一つの提案を示すものです。とくに1章では,算数教育に関する基本的で重要な考え方をまとめました。
小・中学校の教育,教科指導を考える(研究)するなかで,著者と同様に“算数教育の状況に問題・課題”を感じています。
著者の提案に同意するものの,「この本を読み,この本で学ぶのは,誰だろう。」は,読み終えても答えが見えませんでした。
一般書として陳列されていましたが,教員を目指す大学生が「算数指導の教科書」として,小学校の先生が「教材研究の資料」として手にしやすい書架が相応しい図書だと思います。
小学生の算数指導に関わる皆さん,本書で「これからの時代(AI時代)」の算数教育を考えてみませんか。
目次
まえがき
第1章 基本的な考え方
第2章 数と計数
第3章 図形
第4章 量と変化
第5章 場合の数とデータの活用
付録 小学校学習指導要領(算数編)との対応
参考文献
索引
【おまけ】
This channel is a video project that takes videos while walking around cities in Japan and tells people around the world a real life of Japan. I would be glad if people become familiar with the lifestyle of people and towns in Japan through the videos delivered by this channel. Since all the images are taken while walking, I think that viewers can enjoy having a real visual experience as if they are actually walking in the city of Japan.