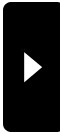2020年12月21日
冬至。昔の炭焼(2) (つくで百話 最終篇)
 低温注意報の出る気温が低く寒~い一日でした。
低温注意報の出る気温が低く寒~い一日でした。そんな寒さの中。いつもより早く蕗の薹(ふきのとう)が出ているのを見つけました。自然の力,大地の力を感じ,感謝しました。
今日は,二十四節気の一つ「冬至」です。一年で昼が一番短く,夜が一番長い日です。「一陽来復」,日の長さは徐々に伸びていきます。
「いちようらいふく」と言葉は聞きますが,文字を気にしていないことはありませんか。以前,「一陽来福」と書いてあって,“福”を呼び込もうという言葉と思っていたことがあります。
「一陽来復」は,五経の一つ「易経」に出てくる言葉です。
復、亨。出入无疾、朋來无咎。反復其道、七日來復。利有攸往。陰暦10月に陰がきわまり,冬至に陽が初めて生じます。そして,冬至を境に日が長くなることから,冬至に太陽の力が復活してくるのです。
「復は亨る。出入疾(やまい)なく、朋(とも)来たりぬに咎(とが)なし。反復その道、七日にして来復。往くところ有るに利(よろ)し。」
新型コロナ禍の状況や社会の動きは,陰が極まった感じです。
ここから,一陽来復よろしく,陽の力がわいてくることを信じています。
『つくで百話 最終篇』(1975・昭和50年7月 発行)の「民族と伝承」の項からです。
********
昔の炭焼 遠山義一
(つづき)
炭窯を築くときには,原木の寄せ集めや水都合の便否を調べたり,風の方向,日あたり具合などを考えて位置の選定をしました。大昔は,山の傾斜面に向って炭窯の形に掘り込んで,壁も天井も自然の土で,ヘッツイのようなものだったそうです。その中へ原木を入れて,外から火を焚いていましたが,中々窯の中へ火が廻らず,燻っていて容易に炭にならず困ったそうです。或る日,不動尊を信仰していた若者が,例によって顔を真黒にしながら一生懸命火を焚いていると,不動尊が現われて「これでは駄目だ」といって,窯の後側に,持っておられた不動の降魔の利剣を突きさして穴をあけられた。そうすると,ここから煙がでて,焚いている火が窯の中へ吸いこまれて,炭が焼けるようになりました。それから煙のでる穴を「フド」と呼ぶようになったといわれております。また一説によると,弘法大師が支那へ留学されたとき,炭焼の方法をも研究して帰朝せられ,窯を築いて炭焼を教えられた。その時から,窯から煙道へ煙の出るところを,大師穴ということになったともいわれておりますが,真偽は定かでありません。
 炭窯の形は,黒炭では,四角形・長方形・楕円形・円形・卵円形などいろいろありましたが,卵円形のものが多くなりました。白炭では,窯の保熱を利用して焼よいようにするという考えから,麦粒形(麦を二つに割った形)・長卵形・卵円形などとなりましたが,卵円形が最も多い窯形です。
炭窯の形は,黒炭では,四角形・長方形・楕円形・円形・卵円形などいろいろありましたが,卵円形のものが多くなりました。白炭では,窯の保熱を利用して焼よいようにするという考えから,麦粒形(麦を二つに割った形)・長卵形・卵円形などとなりましたが,卵円形が最も多い窯形です。大昔の炭窯の,屋根や山小屋は萱で葺きましたが,火事の心配もありましたので,だんだん杉皮葺となり,近年は亜鉛板を用いるようになりました。萱・藁・菰等で屋根を葺く場合には,窯口をはさんで左右両側に,六尺から八尺の高さの柱を合掌にたてて,前記の材料で屋根を葺きました。煙道の上にも,適宜の高さで小屋根をつくりました。
炭窯の壁面は山石で積みましたが,時代がたつにつれて石垣の表面に粘土を塗って,空気もれを防ぐことにしました。
窯の入口は石積にしましたが,その上壁の部分は細長い石をかぶせて支えとしました。窯の奥に煙出しをつくるのですが,その良否によって,炭の品等が決まるといわれて,炭焼の秘伝として他人に知られないようにかくしたものでした。一つの炭山を焼き終って他の山へ移るときには,これを破壊して他人に見られないようにしたものです。ベテラン炭焼の,フド造りの秘伝を盗むために炭焼の娘と交際をして,入婿になったものもあったときいております。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「つくで百話最終篇」〉で
注)『続 つくで百話』の記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
2020年12月20日
『仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ』(川上徹也・著)
 晴れた日ですが,気温が低く寒い一日でした。
晴れた日ですが,気温が低く寒い一日でした。午後,今年最初の映画鑑賞会で,つくで交流館に出かけました。
クリスマスフェスタ2020の催しが行われており,作品展示を見学する人や参加する方がみえました。
久しぶりに大きなスクリーンで,映画を楽しみました。楽しかったです。
「いい話の図書館」で23冊目の図書『仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ』(ポプラ社・刊)
「いい話の図書館」で届く本には,“本に恋する店主の呟き新聞”を使ったブックカバーがかけてありますが,この本にはありませんでした。
今回の新聞は,
恥ずかしくもあり,嬉しくもあり。2020年12月15日,わたしが関わった本が出版されました。ライターの川上徹也さんがあろうことか,わたしのことをフィクションの中に実名で書いてくださったのです。(略)と本書の紹介で始まっていました。
本書の“尼崎の小さな本屋”は,店主 小林さんの店です。そして,主人公 大森理香の“憧れる”人,そして“学ぶ”語りをしてくれるのが,店主 小林さんです。
主人公 大森理香は「それなりの大企業であることが何よりも重要」との思い(?)だけの“甘い就職活動”で,出版取次の大手企業「大販」に就職した“新入社員”です。
東京生まれの大森は,赴任先の大阪は初めての地です。
人生で初めて「ネェちゃん」と呼ばれたこと(略) なぜか私が新入社員とわかったこと(略)自己紹介をすれば「はい15秒経過。ぜんぜんおもしろない」と言われ,何も分かないまま「今日からに決まってるがな」と連れ出されと,困惑(?)しながら新入社員として働き始めます。
いろいろな感情がゴチャ混ぜになって,いきなり涙が出そうになった。
大販の社員として文越堂書店堂島店での研修が始まります。
そこで出会う人,経験することが,新入社員 大森を“人”として成長させてくれますが,この時はまだ気づいていません。
研修で迷い悩む大森を,上司の中川係長が尼崎市にある小林書店に連れていきます。
大森に,店主 小林由美子さんが“長い話”を語ります。それを聞いた彼女に“気づき”が生まれます。
エピソード① なぜ本屋が傘を売り始めたのか?“書店なのに傘を売る”という不思議な話から“感じたこと”,そして“気づいたこと”は,大森にとって新鮮で,彼女に考えさせます。そして,彼女は店主のアドバイスを素直に聞き,“動き”ます。
その“行動”が,大森の何かを変えます。彼女の働き方に,生き方に…。
本書を読むとき,エピソードの前と後で,ちょっと立ち止まってはいかがでしょう。
エピソード② なぜ本屋を継いだのか?エピソードの前で,主人公 大森と自分の今を重ねます。
エピソード③ 小林書店の強みとは?
エピソード④ 鎌田實先生講演会
エピソード⑤ アマゾンに勝った話
エピソード⑥ 夫 昌弘さんの話
エピソード⑦ 本屋にとって取次は親
エピソード⑧ 泥棒に入られる
そして,店主の語るエピソードを聞きます(読みます)。
エピソードを読み終えたら,「自分だったら,どうするか?」と,この後の行動を考えてみます。
そこから,大森の行動したこと,アイデアを,自分の考えと比べながら読み進めると,自分の働き方,生き方への“気づき”が生まれます。そこに学びがあり,あなたの成長のきっかけが生まれることでしょう。
あなたも「○○で大切なこと」を“尼崎の小さな本屋”で学びませんか。
すべての人にお薦めの一冊です。
【関連】
◇川上徹也 (@kawatetu)(Twitter)
◇佳奈 (@kana_gnpk)(Twitter)
今回の「本を愛しすぎた店長小林由美子が選ぶ “おすすめ○○”」は,次の3冊が紹介されています。
【生きることが楽になる 3冊】こちらもお薦めです。
◇『すべてがうまくいく』(松下幸之助・著/PHP研究所・刊)
◇『人生は、だまし だまし』(田辺聖子・著/角川書店・刊)
◇『本所おけら長屋(七)』(畠山健二・著/PHP文芸文庫)
【「いい話の図書館」】
◇最近紹介した本
◇『未来のだるまちゃんへ』(かこさとし・著)(2020/12/09)
◇『リト』(山元加津子・著)(2020/10/27)
◇『ありがとう私のいのち』(星野富弘・著)(2020/09/21)
◇『いわずにおれない』(まど・みちお・著)(2020/08/20)
◇『バケモンの涙』(歌川たいじ・著)(2020/07/31)
*以前に紹介した本は
☆カテゴリー「いい話の図書館」から
「いい話の図書館」とは… 本との出逢いは,人生を変えます。辛い時,悲しい時,苦しい時,一冊の本が「生きる希望」を授けてくれます。
そこで,ステキな本との出会いを提供する「いい話の図書館」を全国津々浦々に作ったら,どんなに素晴らしいだろうと考えて館主を募集しております。「いい話の図書館」の館主のお仕事は,本棚にステキな本を並べて多くの人に自由に読んでいただくこと。そのステキな本は,テレビをはじめ,マスコミでも話題の小林書店のカリスマ店主,小林由美子さんが心を込めて推薦する本です。
◇いい話の図書館【申込】
◇小林書店さん (@cobasho.ai)(Instagram写真と動画)
◇志賀内 泰弘(Facebook)
2020年12月19日
正月の蘊蓄(3)。『首里の馬』(高山羽根子・著)
 寒い一日,朝は雪が舞いましたが,日中は青空でした。
寒い一日,朝は雪が舞いましたが,日中は青空でした。毎年,正月を前に“屠蘇散”を求めて薬局などに寄りましすが,最近「置いていません」と言われることが増えました。
正月の食卓に“屠蘇”は並ばない家庭が増えたようで…。
◇屠蘇お宅の雑煮は,どのような味付け,餅を使いますか。
一年の邪気をはらう祝い酒です。「屠蘇延命散」とも言います。
・屠… 退治する,邪気をはらい寿命を延ばすという謂われがある。
・蘇… 病を起こす悪魔のこと。
屠蘇散は,一般的には「白朮」「桔梗」「桂皮」「山椒」「防風」などの生薬を配合した漢方薬です。大みそかに屠蘇散,みりん,清酒を酒器に入れておいて「薬酒」にしたものを,屠蘇としてお正月に飲みます。
◇雑煮
正月に雑煮を食べるのは,武士の時代の名残です。雑煮は武士にとって一番大切な正式の肴でした。雑煮を立派な秀衛椀に盛って出すのが,武士の宴会の始まりだそうです。
宴会に先だって,必ず主君と家臣の間で盃の応酬が行われました。これを“式三献”といいます。三つの盃が行ったり来たりしますが,その最初の盃が主客の間を回ることを「初献」といい,そのあと「二献」「三献」と続いて盃が納まります。それぞれの盃が回るごとに肴が変わります。その初献の肴が「雑煮」です。
つまり,雑煮がなければ式三献が始まらないし,式三献が始まらなければ宴会が始まりません。すべての宴会は雑煮から始まったのです。
一年の始まりである元旦の朝に雑煮を食べるのは,ここからきているといわれます。
また,雑煮は,地方によって,家庭によって違いがあります。お雑煮の材料,調理法,餅の形はさまざまな種類がありますが,汁は関東風の「すまし仕立て」 ,関西風の「みそ仕立て」などがあり,餅は一般的に,東は「切り餅」,西は「丸餅」を入れる所が多いようです。
図書館に,芥川賞・直木賞の受賞作品が並んでいました。それを見ながら「最近の作品を知らないな…」と,関心をもっていなかったことに気づきました。
黒い背景に,馬,羽根,本,花,骨…が並ぶ表紙にひかれて,第163回芥川賞受賞作『首里の馬』(新潮社・刊)
芥川賞の選評に,
吉田修一氏 ; 高山さんはおそらく「孤独な場所」というものが一体どんな場所なのか、その正体を、手を替え品を替え、執拗に真剣に、暴こうとする作家なのだと思います。とあり,著者の描く“孤独”を楽しみに,そして,小説の“奥行き”に触れたいと思いました。
宮古馬の登場のさせ方は鮮烈で、この宮古馬もまた孤独の象徴だと読めば、そこには体温があり、怯えがあり、臭いがあり、疲れもある。
川上弘美氏 ; 『首里の馬』の中にある静かな絶望と、その絶望に浸るまいという意志に、感じ入りました。一読、すぐに○をつけました。再読し、さらにこの小説の奥行をさぐりたくなりました。
主人公は,沖縄で一人暮らしをしている未名子です。沖縄の歴史を集めた個人の資料館から話が始まりますが,それはボランティアで収入を得る仕事は別にあります。
遠くにいる知らない人たちに向けて,それぞれに一対一のクイズを出題する。仕事の正式な名称は『孤独な業務従事者への定期的な通信による精神的ケアを知性の共有』。通称は問読者,というらしい。(略)
この仕事は企業のサポートセンターでもなく,また勧誘業務でもない。ウェブカメラの動画通信を利用するので,相手には自分の姿が見えてしまう。相手がどんな人間かも,つながるまでこちらはわからない。
題名にある“馬”は,台風の後,未名子の家の庭に静かに登場する「宮古馬(ナークー)」のようです。
この馬は,どこから来たのか,そして何故人に慣れているのか,未名子と,どのように関わっていくのか…。
問読者として話すヴァンダは,この馬のことを聞いて,
「トーテムという思想があります。これは土地の,あるいは一族ごとの単位での思想であったり,また個人的なものであったりします。その人を守る,主語をするものの存在といったものです。形としては獣や鳥,魚などの動物や,植物の場合もあります。集団の場合はその思想の統制などの社会学にも関わりますし,個人の精神守護に関する動物であれば,サイコロジーの領域で語られることもあります」と未名子に話します。
この後,未名子は…。
もやもやしながら読み,そして読み終えました。
「すっきりした」とはならず,そこに謎が…。
この謎を…,話の解釈を…,読み手に任されているようです。
わたしは…。
【関連】
◇高山羽根 Haneko Takayama (@HighMt_HNK)(Twitter)
◇芥川龍之介賞(公益財団法人日本文学振興会 - 文藝春秋)
【参考】

2020年12月18日
正月の蘊蓄(2)。昔の炭焼(1) (つくで百話 最終篇)
 晴れた日になりましたが,積もった雪はなかなか溶けずにいます。
晴れた日になりましたが,積もった雪はなかなか溶けずにいます。当地へお越しになった方には「峠を越えると,そこは雪国だった…」という景色かと思います。
さて,前回に続いての「正月の蘊蓄」です。
◇しめ飾り鏡餅は,三方に半紙を敷いて飾りますが,お宅には“三方”がありますか。
しめ縄で作ったお飾りです。正面玄関の軒下に吊します。家の中にある古い年の不浄を払って,いつも神様をお迎えできますという印です。
正月に門松や,玄関,床の間,神棚などにしめ縄を張って,人間に災いをもたらす禍神が家の中に入ってこないように,呪いとして飾られます。
しめ縄は,左ひねりが定式で,これは左を神聖視する旧来のしきたりによります。
飾りには,輪飾りや,大根締め,牛蒡締めなどがあり,餅,昆布,松葉,魚,橙等を付けて飾ります。
◇鏡餅
神様へのお供えものです。最後に,それをさげていただくのが習わしです。鏡餅は,生命力をもたらすとされました。
鏡餅のお飾りには,
・うらじろ … 長命をあらわす
・ゆずり葉 … 後の世代まで長く福をゆずる
・だいだい … 家系が代々繁栄する
・昆布 … よろこんぶ
・干し柿 … 幸福をしっかり取り込む
・伊勢えび … 海老の中でも最も立派な海老で,腰が曲がるほどの長寿を願う
『つくで百話 最終篇』(1975・昭和50年7月 発行)の「民族と伝承」の項からです。
********
昔の炭焼 遠山義一
 昔の作手郷の山々は,大部分共有山──モヤイ林でありました。モヤイ林は,草刈場と萱場と雑木山でした。杉・桧の植林は,明治になってから盛に行われるようになりましたが,それまでは天然生の赤松が主体をなしておりました。
昔の作手郷の山々は,大部分共有山──モヤイ林でありました。モヤイ林は,草刈場と萱場と雑木山でした。杉・桧の植林は,明治になってから盛に行われるようになりましたが,それまでは天然生の赤松が主体をなしておりました。炭焼をするためにモヤイ林に入る時は,藁の苞を入口に引っかけておいて仕事にかかるのでした。後からきた人は,藁苞のかかっている山には入山せず,他の山を探すことにしました。後世になると,よい山を奪い合う傾向がでましたので,くじ引で山を割り当てることにしました。
その頃の山村の百姓は,現金収入の途が殆んどなかったので,炭焼は恰好の現金収入の稼ぎ場でしたから,炭焼で金を貯めるということに百姓の夢がかかっておりました。そんなところから,全国各地で炭焼長者の話も生れたことでありましょう。
百姓たちは,秋の終りからあくる年の三月までは,一生懸命炭焼に精出したものでした。
その頃,モヤイ林の雑木は,村人は誰でも自由に伐ることができましたが,明治時代になって個人所有の山林が多くなると,山持の人の山を買って炭を焼くか,山主に頼まれて焼子として働くかしたものでした。
炭山を買うときには,その評価が大切で,百俵はでると思った山で八十俵しかでなかったら,「はずれた」といい,その反対に,百二十俵もでると「当った」と喜んだものでした。
炭焼は,その村の住民が大部分でしたが,他所者も入り込んできました。それらの人達は,山持や炭商人の焼子として働いたものでした。炭山へ入山するときには,米何斗・昧噌何貫とかの食料を支給して貰って,炭窯ができて第一回の出炭がある迄の生活を支えました。こんな粂件で仕事にかかるのでしたから,一俵でも多く焼かねば日当にならないので,遮二無二稼いだものでした。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「つくで百話最終篇」〉で
注)『続 つくで百話』の記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
2020年12月17日
昔の作手の山林(3) (つくで百話 最終篇)
 昨夜から雪が降り続きました。朝,数センチの積雪でした。出勤の車が,ゆっくりと動いていました。
昨夜から雪が降り続きました。朝,数センチの積雪でした。出勤の車が,ゆっくりと動いていました。日中,晴れて道路などの雪は溶けましたが,気温は上がらず低いままで,田畑は白い景色のままでした。
明日は…。
『つくで百話 最終篇』(1975・昭和50年7月 発行)の「民族と伝承」の項からです。
********
昔の作手の山林
(つづき)
作手郷でも,幕末から明治初年へかけて,各部落の先覚者たちが申合せて植林を始めた。その主なるものを挙げると,守義の原田紋右衛門・菅沼の原田三十郎・木和田の木和田利兵衛・木和田周平の四氏は大々的な植林を企てた。
田原の中川忠三郎家・中川太次郎家は,隣り同志でスギの美林を造成した。鴨ヶ谷の鈴木縫十氏の裏山のヒノキ林と,鴨ヶ谷沢のスギの美林は,大正中間まで見事な林相を誇示していた。
戸津呂の佐宗武平氏・井上和吉氏・和田の佐宗孫兵衛氏・見代の加藤藤吉氏等は,立地条件に恵まれてスギの美林を造成した。
赤羽根の石原弥四郎氏のトンゴウチのスギ林・小林の峯田文重氏・大和田の島幸市氏等の造成したスギ林は,今もその偉容を伝えている。
 杉平の峯田与長治氏の千本立ちのスギ林は,明治時代の作手を代表する美林であった。
杉平の峯田与長治氏の千本立ちのスギ林は,明治時代の作手を代表する美林であった。作手郷に数多くあったスギの美林は明治初年からの植林であったが,太平洋戦争中の強制伐菜で大半姿を消してしまった。僅かに残された百年生からのスギ林は,稀少価値の骨董品的存在となった。
江戸時代に大半を占めていた入会山は,明治時代になると順次入札払下げによって地元民の個人所有となり,スギ・ヒノキの植林が盛に行われた。明治末年には,小学校基本財産として学校林三〇〇ヘクタールの造成が計画され,入会林がこれに充てられた。大正時代になっても,まだ一四四一ヘクタール余の入会山があったが,大正十三年の公有林野統一事業で,四〇〇ヘクタールの村有林造成と,地上権付与地四八八ヘクタール余の設定によって,作手の山林に占める入会山の比率は極めてわずかなものとなった。
太平洋戦争中の濫伐によって,森林の立木蓄積は著しく低下したが,戦後の造林奨励で植林面積は格段の飛躍を遂げた。往年の,巨木造成主義は優良材造成へと転化した。中部高原地帯は,木曽谷に匹敵するヒノキ造林の適地であり,南部・北部の肥沃な林地帯は,全国有数のスギ造林の適地でもある。先進林業地の技術をとりいれた作手の山林が,未曽有の盛観を現出する日も遠いことではあるまい。
(峯田通悛)
********
注)これまでの記事は〈タグ「つくで百話最終篇」〉で
注)『続 つくで百話』の記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
2020年12月16日
正月の蘊蓄(1)。昔の作手の山林(2) (つくで百話 最終篇)
 今朝,覚悟して外を見ると“真っ白”でした。一面の雪景色でした。
今朝,覚悟して外を見ると“真っ白”でした。一面の雪景色でした。今日も「最高の感染者数で…」と伝える状況ですが,昼食で寄ったモールの店舗は“長い列”が出来ていました。
蜜を避け,予防に努めているとはいえ,自分も含め「用事があるから…」と人出は多くなっているようです。この人出を止めるのは「○○の中止」ではないでしょうね。
みなさん,気を付けましょう。
“正月事始め”から続く「正月の蘊蓄」です。
◇お正月に用意するもの門松は,松とは限らず,榊,栗,楢,椿等の常緑樹であれば,何でもよかったのですが,今では松がほとんどです。竹を一緒に飾るようになったのは,鎌倉時代からだそうです。
門松,しめ飾り,鏡餅,おせち料理,屠蘇…
◇門松
神様が家々に降りてこられるための依り代です。門前を清めて年神様を迎えます。
新年を祝って,家の門口等に立てられる松竹の飾りです。松飾り,門の松とも言われるそうです。
古くは,木の梢等に神は宿るとされ,門松はその依り代として,そこに年神様を迎えて祭りました。
門松を取り付けるのに,12月29日は「苦立て」,12月31日は「一夜飾り」といい,この日に門松を立てるのを嫌います。
今年,お宅では門松を立てますか。
『つくで百話 最終篇』(1975・昭和50年7月 発行)の「民族と伝承」の項からです。
********
昔の作手の山林
(つづき)
作手高原の或る部分のヒノキには,木曽ヒノキと同様な優良材質のものがある。学者の調査によると,ヒノキもスギも五〇年以上になると主幹にネジレがでてくるが,その方向がヒノキとスギでは逆になる。ヒノキのネジレ具合が,いわゆる木曽材といわれるものに似たものが作手にある。
作手郷の山林には,各地に領主が支配していた「お林」(お留山,またはお立山ともいった)があったが,大部分は入会山(モヤイ山)であった。入会山は百姓の草刈山で,薪炭などはここでつくられた。立木は,マツ・スギ・ヒノキなどが,ポツリポツリたっているにすぎなかった。
応暦二年(1339)伊勢神宮御造営について,設楽山から御用材を伐出したという記録がある。設楽山というのは,設楽町神田の入にある一の又・椎代山であろうと推定されているが,この山なら,直ちに三輪川に狩落され,管流しで小川・乗本辺に集められ,ここで筏に組んで吉田港へ送り,それから三河湾を横ぎって伊勢の大湊港に運ばれたものであろう。何れにしても,奥三河の設楽山が神宮御用材を仰せつけられたということから,地続きの作手郷にも,スギ・ヒノキの美林が存在したことが想像される。
昔の林業といわれたものは,山へ入って木を伐り,出材して製材する仕業であったが,戦国時代になると,諸大名の城廓建築・武家屋敷や城下町の造成が急激に進み,木材の需要は止まる所を知らぬ有様となった。寛文~享保の江戸時代になると,この傾向は一層烈しくなり,各地の有名林業地は立木を伐り尽して所謂・尽山現象を招くことになった。先覚者・熊沢蕃山などは,夙にこれを憂い「天下の山林十に八尽き候」と警告して,領主に植林を勧奨している。
この尽山現象は幕府も放置することができず,寛文二〇年(1643)八月二六日「郷村御觸」の一節で「御料在々所々山林に仕る可き所は木苗を植え置き山林をば以来其村の助けにも罷り成り候様に仕る可き事」と命じている。次いで承応元年(1653)正月四日の代官服務心得の中で,「自然の障りにもならざる荒地山野等これ有らば苗木を植え山林を仕立る可きの旨申し付けらるぺき事」と,植林を命じている。
作手村についての文書は見当らないが,鳳来町池場の金田家文書によると,今から二百五十年くらい前から役人の指令で,スギ・ヒノキ苗の挿植えをしている。その記録によると,スギの挿苗は半分くらい活着しているが,ヒノキは成績が悪かったようである。金田家では,自家山林から実生のスギ苗を菜集して畑付けして,六〇センチくらいに成長したのを山植えしている。この実生苗とりを「子生え拾い」または「子拾い」と言っていた。戦前,金田家のお台所山として県下に知られた美林は,かくして造成されたのであった
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「つくで百話最終篇」〉で
注)『続 つくで百話』の記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
2020年12月15日
初雪,積雪…寒い。『70歳のたしなみ』(坂東眞理子・著)
 天気予報通りに寒い日になりました。
天気予報通りに寒い日になりました。しかも朝は景色が白く,雪が積もっていました。これが,当地の初雪です。
田畑は白くなっていますが,近くの道路は溶けていました。
寒い日が続くようですので,明朝の道路凍結が心配です。通勤の方はお気を付けください。
出先に向かうとき,豊田市まで雪が降り,気温は3度でした。その後,雨に変わりましたが,出先の気温も3度のままでした。
途中のガソリンスタンドは,いつもと違うようすでした。タイヤ交換(?)を待つ車がたくさんいました。帰りにも交換作業が続いており,車の列がありました。職員の方々は休憩時間もない一日だったかもしれません。お疲れさまです。
新型コロナウィルス感染の拡大が続いています。感染予防がさまざまな形で呼びかけられますが,宮沢孝幸氏(京都大)が発生当初より言われている「100分の1に減らす作戦!」が,分かりやすく大切な取り組みです。
寒い日も,部屋の“換気”には気を遣い,手指を洗い,感染予防に努めましょう。

『国家の品格
それ以降,「○○の品格」と題した本が多数出版され,テレビ番組などのタイトルともなっています。
そのなかで,坂東眞理子氏の『女性の品格
その坂東氏の新著が“シニア本”の書架にありました。題名が気になったのか,著者にひかれたのか,『70歳のたしなみ』(小学館・刊)
現在72歳の著者は,「はじめに」で,70歳について,次のように述べています。
最も人生で幸福なのはいつ頃か──と問われたら現代では70代ではなかろうか。(略)“たしなみを持って希望とともに生きていく”こととして著者の考える10項目。
自分の人生を少し高い視点から俯瞰し,総括する境地に立って,続く80代や90代に備える心の用意ができる時代である。かつては60歳が還暦として人生の節目とされたが,今は70歳が人生の節目であり,次のステージへの出発点になるのではないか。
その貴重な70代を,人生70年時代の先入観のまま晩年として生きるのはあまりにももったいない。
1.機嫌よく過ごすように努める。この考えから,「70歳。~」と4章32項目で述べています。
2.年齢を言い訳にしない。「今さら」「どうせ」「もう遅い」と言わないで,まだまだ成長の余地があると考え努める。
3.今まで受けた恩を思い出し,感謝を忘れない。
4.できる時にできる範囲で人の世話をする。
5.周囲の人,若い人の良いところを見つけて褒める。
6.キョウヨウとキョウイクは自分でつくる。
7.人は人,自分の人生を否定しない。つらい経験があったから今がある。
8.今こそおしゃれ。
9.健康第一もほどほどに。
10.孤独を楽しむ。
先の10項目,そして目次を読んで,「何だか説教のような…」と感じる方がみえそうです。どの項目も,それを外さない語り口ですが,その内容は,「たしかに」「なるほど」と合点するものです。
気になる内容を順序を変えて読んだり,拾い読みしたりしても,“イメージ・チェンジ,マインド・チェンジ”をするヒントが得られます。
70歳からのゴールデンエイジを生きる人に向けて書かれていますが,「まだまだ先のこと…」という若い人にも,日々の過ごし方の教科書となる一冊です。
みなさん,いかがですか。
読書メモ
○ 頼まれるのを待つのではなく,自分から手をあげる。「ノックしないドアは開かない」のである。ノックもせず,空しい,物足りない,手ごたえがない,と思っていてもドアは開かない。
○ 特に新聞,テレビのような旧メディアは高齢者向けの(略)
若者向けのモノやサービスはネット広告が主流になっているので,新聞やテレビは高齢者にターゲットを絞っているのだろう。
○ ここ10年来,歳をとったらキョウヨウとキョウイクが大事だと言い続けてきた。今日は用がある,今日は行くところがある,ということである。
○ そうならないとめには「欲をかかない」ことに尽きる。
○ ケネディ大統領の有名な就任演説にある(略)
「若い者が君のために何ができるかを問うのでなく,君が若い者のために何ができるかを問いたまえ」と。
○ 恩返ししなければと思うと負担になるが,「恩送りでもいいのだ」と視点を変えると気が楽になる。
○ これからの世代を応援する節度や慎みを持って一日一日を積極的に生きる。そうしたたしなみのある高齢者には,おのずと品格が備わります。
目次
はじめに イメージ・チェンジ、マインド・チェンジ
第1章 今こそ「いい加減」に生きる知恵を
70歳。意識して上機嫌に振る舞う
70歳。まだまだ未熟、まだまだ成長 他6項
第2章 始めるべきは「終活」ではなく「老活」
70歳。今日が人生で一番若い日
70歳。過去にはこだわらない 他6項
第3章 あなたにできることはたくさんある
70歳。「私への挑戦」を新たに始める
70歳。コンシアージュになる 他6項
第4章 品格ある高齢期を生きるために
70歳。生活設計から目を背けない
70歳。単一のお手本がないことに感謝する 他6項
あとがき 私たちが幸せになるために
【関連】
◇理事長ブログ:坂東 眞理子のオンとオフ(昭和女子大学)
2020年12月14日
昔の作手の山林(1) (つくで百話 最終篇)
 “寒い一日”でした。
“寒い一日”でした。冬型の気圧配置となり,雲も“雪雲”のようで,日が出ても暖かさはありませんでした。今夜から明日にかけて雪が降るとの予報があり,初雪,初積雪となかもしれません。
気を付けましょう。
『つくで百話 最終篇』(1975・昭和50年7月 発行)の「民族と伝承」の項からです。
********
昔の作手の山林
日本列島は,洪積世代の百万年から一万年くらい前の間に,四回氷期に襲われている。それまで作手の山野に生育していた植生も動物も,殆んど絶滅したものと思われる。現在ここにある植生や動物や人間などは,その後迎えた暖期以降に根づいたものであろう。
最初に発生した苔・シダ・ヨシなどにつづいて,常緑潤葉樹が繁茂し,落葉澗葉樹,針葉樹ヘと広範の植物をうみだしたものであろう。日本のスギの古木としては,九州屋久島の縄文杉が七〇〇〇年,同地の大王杉が三〇〇〇年くらいと推定されているが,市場の古宮や,相月の白鳥神社の境内には,一四〇〇年くらいのスギ・ヒノキが現存している。村内各地の神社仏閣の境内にあるスギの古木には,五〇〇年~一〇〇〇年と推定されるものが多数見うけられる。終戦後間もない頃,田原地内の河川改修工事の際,地下五~八メートルの粘土層上に,水平に横臥している埋木が多数発見されている。中には,最長三〇メートルにも及ぶ巨木もあり,埋木の多くは深根性のもので,樹種は次表のようである。
埋木が,泥炭層下二~三メートルにあることと,泥炭の堆積速度が年間一~数ミリメートルといったことを考えると,相当の年月を経過していることが推定される。
 この埋木は,作手湿原がその発達段階上,全国的にも稀な「中間湿原」とも見なされ,埋木はその一つの特徴条件である。なお,この埋木地帯は,作手湿原下の全部に分布していることが判明した。殊に長野山のものは開墾の結果,地表に露出した枝葉・果実等は材部の周辺に半化石として残っている点から考えても,相当旧いものに違いない。また,川尻地区の河川改修時には,地下三~五メートルからも発掘されている。
この埋木は,作手湿原がその発達段階上,全国的にも稀な「中間湿原」とも見なされ,埋木はその一つの特徴条件である。なお,この埋木地帯は,作手湿原下の全部に分布していることが判明した。殊に長野山のものは開墾の結果,地表に露出した枝葉・果実等は材部の周辺に半化石として残っている点から考えても,相当旧いものに違いない。また,川尻地区の河川改修時には,地下三~五メートルからも発掘されている。大正末期の頃,川尻・田原地内に,中川忠三郎家の見事なヒノキ山があった。樹令三〇〇年といわれていたから,恰度木曽国有林のヒノキと同年代に生じた天然林であった。今から三六〇年くらい前に,笹や竹にジネンゴがついて全滅したことがあった。その禿山に生えたヒノキが生育したのが,木曽のヒノキ林であったといわれているが,作手郷にも木曽谷と同じ現象が出現したものと思われる。
(つづく)
********
注)これまでの記事は〈タグ「つくで百話最終篇」〉で
注)『続 つくで百話』の記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
【感染症メモ】
「正しく恐れ,不安と付き合う」ことを。
先週の週刊誌で読んだ岩田健太郎(神戸大学)の話から。
○ まず断っておきたいのが「今日の感染者は何人」といった日々の数字に振り回されるベきではないということです。第3波で言われる「勝負の3週間」は,誰(何)に勝負をかけ,何時(いつ)のどのような結果を求めているのかで,「3週間」の具体的な期間が変わってきそうです。
○ コロナに感染してから発症までにざっくり1過間。
○ 発症後,数日症状が続いて検査を受ける。
○ 検査の結果が集計されて報告されるまでに10~14日。
○ さらに重症化する場合は数日を要する。
○ その患者が回復する,あるいは亡くなるまでに数週間。場合によっては数か月かかる。
○ 従って,今われわれが見ている「数字」は現在の数字ではありません。
○ 現状の認識も,将来の予測も,(略) それらの変化のトレンド(傾向)を前提に考える必要がある。
2020年12月13日
「正月事始め」の日に。
 朝は晴れていましたが,雲が広がり“冬の空”に変わっていきました。日差しがなく,冷たい風が吹く冬の一日でした。
朝は晴れていましたが,雲が広がり“冬の空”に変わっていきました。日差しがなく,冷たい風が吹く冬の一日でした。先週,“年末年始”のことを話題にしました。
今日13日は,子供の作文にもあった「正月事始め」の日です。
正月に,新しい年神様を迎えるための諸準備を始める最初の日とされました。休日を使って年末の大掃除や片づけを始めた方も多かったのではなかったでしょうか。
正月事始めの最初は「煤払い」です。昔はどこの家にも竈や囲炉裏があったことから,一年間に溜まった煤を取り除き,家の内外を大掃除を行い,煤掃き・煤納めの行事とも言われました。
煤払いの後は「松迎え」です。雑煮を炊くための薪や門松に使う松を山に取りに行きます。新年の年男が新年の恵方の方向にある山に出かけました。
そして,新年までに,もちつき,鏡餅,お節料理,門松,松飾りなどの用意をしていきます。
古い資料(2008/12/18)に,保護者に聞いた「Q 家庭で伝統行事を行っていますか。」の結果がありました。それを「行っている」との回答は次のようでした。
○ 冬至の日にカボチャを食べたり,ゆず湯に入る。 42%12年前とは子育て世代の暮らしも変わり,同じ質問への回答の状況は異なるでしょう。新型コロナ禍で,昨年とも変わっているかもしれません。
○ 大晦日に年越しそばを食べたり,除夜の鐘をつく。 81%
○ 正月に門松やしめ縄,鏡もちなどを飾る。 83%
○ 1月7日に七草がゆを食べる。 26%
○ 1月11日に鏡開きをする。 48%(略)
こうした中でも,伝統や風習を意識していくことは,豊かな暮らしにつながるように思います。
日本の伝統・文化ではありませんが,クリスマスも,すっかり定着した年末の風物・イベントです。
子供達から「新型コロナウイルス感染症で,今年はサンタクロースが出かけられない。サンタやトナカイが感染するんじゃないかと心配だ。」との声があるようです。
◇Google Santa Tracker
日本へ来るでしょうか。そして,お子さんのところへは…。
この時期に,楽しみにしている動画があります。
その一つが Coca-Cola のクリスマスCMです。今年のストーリーは…。
◇Christmas feels special with loved ones and Coca-Cola(1:00 YouTube)
◇Coca-Cola Christmas Commercial 2020(2:30 YouTube)
もう一つは,カナダの航空会社 WestJet です。
2013年に初めて“クリスマスのサプライズプレゼント(Real-time Giving)”を見てから,毎年楽しみにしていますが,まだ今年の作品は公開されていません。
多くの人を笑顔にしてきたWestJetのサンタクロースが,新型コロナ禍でのクリスマス2020を,どのように見せてくれるのか,笑顔になるのか,公開が楽しみです。
◇WestJet Christmas Miracle: To Give or Receive(4:24 YouTube,2019年)
これまでのWestJet Christmas Miracle。
◇WestJet Christmas Flash Mob(3:04 YouTube,2012年)
◇WestJet Christmas Miracle: Real-time Giving(5:25 YouTube,2013年)
◇WestJet Christmas Miracle: Spirit of Giving(5:33 YouTube,2014年)
◇WestJet Christmas Miracle: 12,000 mini miracles(4:49 YouTube,2015年)
◇WestJet Christmas Miracle: Fort McMurray Strong(3:55 YouTube,2016年)
◇WestJet Christmas Miracle: 12 Flights of Christmas(4:03 YouTube,2017年)
◇WestJet Christmas Miracle: Uniting Through Traditions(4:17 YouTube,2018年)
◇WestJet Christmas Miracle(WestJet official site)
あなたが楽しみにしている動画は,どのようなものですか?
2020年12月12日
教育学会研究大会。作手の湿原(2) (つくで百話 最終篇)
 朝,冬の訪れを感じる曇り空でしたが,しばらくして晴れたよい天候になりました。
朝,冬の訪れを感じる曇り空でしたが,しばらくして晴れたよい天候になりました。午後,第51回愛知教育大学数学教育学会研究大会が,オンラインで開かれました。新型コロナ禍で,初めてのオンライン開催となり,新しい構成と内容でした。
○開会のあいさつ(会長)これまでより参加者は少なかったようですが,“新しい提案”を考えることができ,そして活かしていくことができると感じました。
○趣旨説明
○附属学校における取り組み
○大学における取り組み・提案と議論
・コロナ禍における大学教育の実態と反省
・算数・数学の授業のためのソフトあるいは動画コンテンツのあり方
・教員養成における授業動画配信の利用について
・大学・附属学校と地域の学校を結ぶためのオンライン
○閉会のあいさつ
“学び”について考える時間と機会を得られました。
関係のみなさん,ありがとうございました。
師走そして今日を振り返りながら,昔この時期に聞いた言葉を思い出しました。
○ 「蔵の財」「身の財」よりも「心の財」の蓄えこそが肝心。学校の中に,“心の財”を蓄え,“潤い”を持てる時間が流れているでしょうか。
○ どんな本を読んで心豊かになりましたか。
○ 未来の可能性に馳せる希望の目線を常に持ちたい。
○ 教師の話題に,「潤い,情操,希望」がありますか。
○ 教師たる者「書くこと」を軽んじてはいませんか。
○ 得手不得手ではなく,深く考えるために厭わないように心がけたい。
教職員のみなさんが,心豊かに過ごせる学校・環境であることが,子供達の成長に大切だと思います。
『つくで百話 最終篇』(1975・昭和50年7月 発行)の「民族と伝承」の項からです。
********
作手の湿原 権田昭一郎
(つづき)
作手の地名の起原…作手の地名の起原も,善福寺にまつわる伝説などもあるが,本来は「津くて」つまり,水の多い広い湿原に起因したものと考えるのが,最も妥当であろうかと思われる。そこで「くて」の呼び名は前述のように,一般的には,その形や主な植物を冠詞とする場合が多い。ところで「津くて」に限って水を強調していることは,実は大いに意昧のあることである。
作手の湿原…作手の湿原を調べてみると,平野部の「くて」とは大分様子が異っている。一般的に,湿原は浅い沼沢地のまわりから,スゲやヨシなどの植物が徐々に中心部へ侵入し,それが,多湿・酸素不足・強酸性などの理由から泥炭となってできあがっているが,作手の場合は,元来中北部一帯に相当広大な湖水があり,それが短期に脱水し,露出した湖底を一時,スゲ・ヨシなどがおおって堆積し,更に樹木が生えて倒伏し,更に草木の堆積,泥炭化のくりかえしが続いたものであろうと考えられる。湿原地は生きものであるから,年々歳々少しずつ変化するが,その様子で,ミズゴケを沢山もった「高原湿原」と,水の深い「低層湿原」とに分けられるが,作手湿原は今のところ,そのどちらにも属しない「中間湿原」と呼ばれ,全国的にも比較的珍しいものである。
昭和三〇年後半から,四〇年前半にかけて,大字清岳・鴨ヶ谷・高里地域の湿原「大野原」(三〇ヘクタール)を始め,東田原のウキ(五ヘクタール)など,その主なるものが次々と水田に変ったが,幸い大字岩波の「長ノ山湿原」(一〇ヘクタール)の一部が,愛知県天然記念物として昭和四八年十一月二六日に指定され,永久保全のめどがついた。湿原は,その立地粂件が特異であるので,当然のことながらそこには特異な生物相がみられる。植物では,ツクデマアザミ・ミカワイヌノヒゲ・サギスゲ・ヤチスギラン・ミコシギクなど,また昆虫では,ヒメトカゲ・グンバイイトトンボなどは,その主なるものである。
「開発か保全か」が,全国的に問題になる現在ではあるが,このかけがえのない,わずかに残された「作手湿原」を,われわれは天恵の宝として後世に伝承したいものである。
(愛知県立新城高等学校作手分校主事)
********
注)これまでの記事は〈タグ「つくで百話最終篇」〉で
注)『続 つくで百話』の記事は〈タグ「続つくで百話」〉で
注)『つくで百話』の記事は〈タグ「つくで百話」〉で
【参考;「湿原の変遷」「作手地区の湿原」】

※旧作手村作成ののパンフレットより